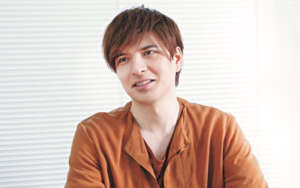32歳で作家になり、わずか5年で直木三十五賞受賞という快挙を成し遂げた今村翔吾さん。ダンスインストラクターや作曲家、埋蔵文化財調査員など異色の経歴で、作家デビュー後も書店の事業承継、「まつり旅」と題した全国行脚など作品以外でも話題を集める。2022年9月末からはラジオで冠番組を持つなど、多方面で活躍する直木賞作家を訪ねた。
教え子のひと言から動き出した小説家への夢
プロ野球選手やサッカー選手、パイロット、宇宙飛行士―、子どもの頃、無邪気に思い描く将来の夢の多くがはかなく散る。歴史小説・時代小説家の今村翔吾さんの夢も例外ではなかった。
「小学5年生のときに、本屋さんでたまたま手にしたのが池波正太郎先生の『真田太平記』でした。あまりの面白さに一気に全巻読破して、池波先生のほかの作品や、司馬遼太郎先生、藤沢周平先生などの歴史小説、時代小説を読みあさりました。自分も大人になったら小説家になる。そう思っていました」
だが、その夢は「思う」で止まった。歴史小説や時代小説は愛読し続けたものの、父親が経営するダンススクールの後継者として、同スクールのダンスインストラクターとしての道を歩み、作曲家としても活動した。スクールは京都を中心に、近畿地方に複数の教室があり、今村さんは約250人の子どもたちを教えていたという。そんなある日、教え子とのやりとりが、その後の今村さんの人生を大きく変えた。
「子どもたちに『夢を諦めちゃダメだ』とハッパを掛けたんです。そうしたら、一人の子から返ってきた言葉が『翔吾君だって、夢を諦めているくせに』でした。衝撃が走りましたね。で、その場にいる子どもたちと約束したんです。『分かった。30歳からでも夢がかなうことを証明したる』って」
子どもの言葉がきっかけとなって、今村さんの夢が動き出した。とはいえ、それまで今村さんは一度も小説を書いたことがない。文字通り、ゼロからのスタートだった。
子どもたちとの約束を果たした直木賞受賞
小説家になると言っても、なれる保証はどこにもない。それでも今村さんは思い切ってインストラクターの仕事を辞めた。なかなかできない覚悟だが、今村さんは「高収入だったら職を変えることをためらったかもしれません。でもその逆だったから、何とかなると腹をくくれました」と笑う。
夢に生きようと決めた今村さんには、もう一つの夢として「歴史に携わる仕事がしたい」という思いがあった。そこで、昼間は当時暮らしていた滋賀県守山市で埋蔵文化財調査員として遺跡の発掘・調査を行い、夜は寝る間も惜しんで執筆した。
「遠い未来に目標を掲げると気持ちがなえてしまうので、短期目標を設定しました。それも長編ではなく短編からのスモールスタートです」と語る。
だが、今村さんは初手から文才を発揮した。2016年1月、初めて書いた短編小説が伊豆文学賞を、2作目が同年3月に九州さが大衆文学賞と立て続けに受賞する。その勢いに乗って、17年に『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』で作家デビューを果たす。その後も発表作は軒並み名だたる文学賞の受賞作や候補作になり、単行本は全て重版の出来となった。
そして22年1月、『塞王(さいおう)の楯』で第166回直木三十五賞(以下、直木賞)を受賞する。わずか5年で売れっ子作家の一人に躍り出たのだ。直木賞受賞作は、戦国時代に琵琶湖畔にあった大津城を舞台に、城の石垣をつくる石工集団の穴太衆(あのうしゅう)と、鉄砲鍛冶集団の国友衆の攻防戦を描いたもの。石の自然の造形を生かして積む穴太衆を描くに当たり、今村さんが取材したのが、くしくも本誌の20年11月号で紹介した粟田建設の粟田純徳さんだ。物語のキーワード「石の言葉を聴け」は、本誌インタビューでも粟田さんが語っている。本職が信条とする言葉だからこそ重く、深く、作中で響いた。
「僕は京都生まれですが、第二の故郷といっていいほど滋賀、それも琵琶湖に魅せられた一人です。滋賀発祥の穴太衆のことは知っていましたが、僕の作品はどれもテーマが先。特定の人物や建造物から物語を展開しないのが特徴です。この作品も日本海のレーダー照射問題に端を発し、争いはどうやって起こり、どう終わるのか、核の抑止力を矛とするなら盾は何か、主人公の石工職人、匡介と一緒に考えながら書きました」
全国行脚の「まつり旅」など執筆以外の活動も活発
直木賞受賞の知らせを受けて「子どもたちとの約束をようやく果たせた」と大粒の涙を流す今村さんの姿は、今も記憶に新しい。だが、その後の行動も世間を驚かせた。直木賞受賞のお礼行脚と称し、47都道府県、約290カ所の書店や学校を巡る「まつり旅」を実施したのだ。訪問先は事前に募集し、「まつり旅」の間も執筆できるようにワゴン車を改造した。かかった費用は旅費を含めてざっと1000万円。5月30日に滋賀県守山市を出発し、118泊119日かけて山形県新庄市でゴールのテープを切った。新庄市はデビュー作『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』ゆかりの地で、大勢のファンが詰めかけた。
「旅は、書店や全国の読者に直接お礼を言いたかったのが第一の理由です。でも裏テーマとしては何のために書くのか、行動して思考を巡らす旅でした」
今村さんは直木賞受賞の3年前に、直木賞候補になったことがある。無名の作家が候補5作品に選ばれた喜びは直木賞受賞と同等、いやそれ以上だったと語る。だが、一躍人気作家の仲間入りをすると、「今村翔吾」の虚像が独り歩きし、実際の自分とのギャップに苦しんだ。
「読者にいいものを届けたいという芸術家としての自分と、売れなあかんという仕事人としての自分との葛藤もありました。作家活動を始めた当初はお金や生活よりも、孤独が一番しんどかった。それまで子どもたちに囲まれていた生活やったからね。その反動もまつり旅にはあります」と語る。旅の道中で多くの人に温かく迎えられ、中には「生まれてきてくれてありがとう」と泣きながらお礼を言われたこともあった。
「何者でもなかった者が、そう言われる者になったと自覚しました」と今村さん。複数の雑誌や新聞連載を抱えながら、講演やテレビ出演をこなし、21年11月には大阪府箕面市の「きのしたブックセンター」の事業承継をして、書店も経営する。さらに「一般社団法人ホンミライ」を立ち上げ、作家や編集者など本にまつわる人と学校をつなぎ、子どもたちに本の魅力や、本と出合うきっかけづくりにも取り組む。「18年から1日も休みなし」と苦笑するが、書店の売り上げを伸ばし、しんじょう観光大使や箕面本屋大使として地域に貢献するなど、多方面で〝結果〟を出している。
「今村翔吾の第2章はこれからですよ」と、まだまだ世間をにぎわす計画は進行中だ。
今村 翔吾(いまむら・しょうご)
歴史小説・時代小説家
1984年生まれ。ダンスインストラクター、作曲家などを経て2017年『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』で作家デビュー。18年『童の神』で角川春樹小説賞、20年『八本目の槍』で吉川英治文学新人賞、21年『じんかん』で山田風太郎賞、22年『塞王の楯』で第166回直木三十五賞を受賞する。21年11月に大阪府箕面市「きのしたブックセンター」の書店経営者を承継。21年しんじょう観光大使(山形県)、22年箕面市特命大使「箕面本屋大使」(大阪府)に就任。朝日新聞朝刊で『人よ、花よ、』連載中
写真・後藤さくら