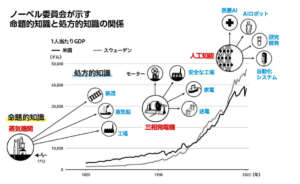米国のトランプ政権は日替わりのように新たな関税政策を発表、世界経済を振り回している。日本をはじめとする各国は、交渉によって相互関税の引き下げを求めているが、大きな譲歩を引き出すことはできないだろう。「関税による米製造業の再生」はトランプ大統領の信念で、政権の存在意義でもあるからだ。日本企業はトランプ関税を前提とした経営戦略に転換せざるを得ない。その時、心掛けるべきことは本連載3月号で述べた「探索と分散」である。
「探索」は関税動向に目を向けることではない。トランプ関税が引き起こす商流・物流の変化、生産地・生産企業のシフト、新たな市場の勃興などに目を向けることだ。もちろん、そうした変化は当初は小さな芽であったり、ささやかな流れの転換だったりするため見落としがちで、見通しの悪い中での動きでもある。だからこそ、手探りで、触手を伸ばして変化を探る必要がある。
振り返れば、米ソ冷戦後の1990年代初頭に始まったグローバリゼーションによって、世界の見通しは画期的に良くなった。ヒト・モノ・カネに加え、情報の流通も劇的に拡大したからだ。「グローバリゼーションの逆流」ともいわれるトランプ関税により、世界の先行きは深い霧の中にある。しかし、ビジネスは動き続けなければならない。「探索」によって得た情報からヒト・モノ・カネを動かしていくわけだが、重要なのは「分散」である。見通しの良い時代には「選択と集中」が企業の利益率を高めたが、トランプ関税時代には「探索と分散」が基本戦略となる。
筆者は4月に中国・広東省の日系、中国系企業の工場を回った。日系企業は日々、変化するトランプ関税と習近平政権の対抗策に翻弄(ほんろう)されてはいるものの、「探索」に動いていた。中国からほかのアジア諸国への生産移管を探り、中国から従来の製品輸出ではなく、部品で対米輸出し、関税対象となる価格を下げ、米国内で組み立てて対応するといった試みだ。
一方、中国企業は国内市場へのシフトを試みていた。「以旧換新(古い製品を新製品に買い換える)」政策など、過去最大級の内需刺激策が実施されているためで、一部のメーカーには、内陸への工場移転によって生産コストを下げ、内陸市場を攻略しようという構想もあった。
いずれも生産の拠点と工程、販売市場の「分散」である。今こそ「探索と分散」を心掛けたい。