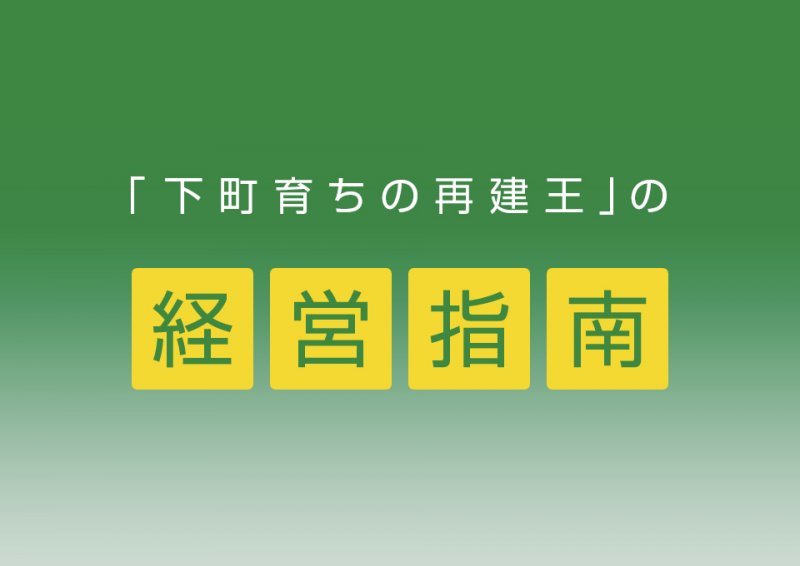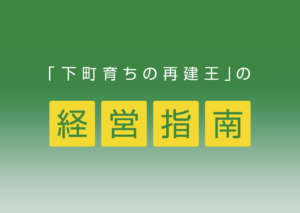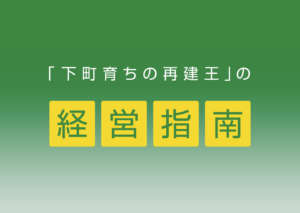師として仰いだ船井総研の創業者、舩井幸雄氏が元気であった頃、「丸井」の青井忠雄会長と私の3人で、年に一度、会食をしていました。お二人より14歳年下の私は出過ぎた会話はせず、もっぱら二人の話に聞き入るばかりでしたが、ある年、私は約束の時間よりだいぶ早く会場に着いてしまい、二人を待っていたところ、その日は青井会長も30分ほど早く到着されて、舩井氏が来るまでの間、江戸っ子同士で蕎麦(そば)談義に花を咲かせました。
蕎麦好きの多くは、それぞれ自分が一番うまいと思う蕎麦屋があるものです。青井会長は、「室町砂場」が一番、「並木藪蕎麦」が二番、そして「吾妻橋やぶそば」の鴨(かも)汁そばが三番、と言い切りました。私の意見は会長の一番と二番が逆でしたが、そのことよりも隠れた名店といわれている吾妻橋を挙げられたことに、大きく相づちを打ちました。
さらに、一番と二番の順序の理由をお尋ねすると、青井会長はしっかりとした根拠をお持ちでした。両店ともせいろ1枚当たりの蕎麦の量が少ないため、2枚や3枚、場合によっては4枚を注文する客もいるほどで、提供する時には1枚目をまず運び、食べ終える頃合いを見て次の1枚を出す形式です。室町では何枚目でもゆで加減が一貫しているのに対し、並木ではまれにゆで加減にばらつきがある、というのが理由でした。私もその点に気付きはしましたが、蕎麦そのものの味は並木が上だと感じたため、結果的に会長とは逆の順位を付けていたのです。
「たかが蕎麦、されど蕎麦」。江戸っ子にとって蕎麦は心遣いや美意識の象徴であり、今なお粋の文化を語る上で欠かせない食べ物です。この短い30分間の会話をきっかけに、青井会長との距離は一気に縮まりました。 日本各地には個性的な蕎麦が数多く存在し、その土地ごとのこだわりや名店があります。これらの蕎麦を通じて多くの人々が交流し、それぞれの楽しみ方や流儀を共有しています。会話のテーマにはさまざまなものがありますが、食べ物談義は単なる雑談にとどまらず、円滑な人間関係の構築と個人的な親しみを生み、相手との距離を縮める魔法のような力を持っています。
私は人見知りで、親しい人以外と話をすることが苦手でした。また、コンサルティング中の早口が原因で怖そうな印象を与えてしまうことがあったようですが、B級グルメが大好きな根っからの食いしん坊であることが幸いし、食をテーマにした会話が糸口となって、多くの方々と仲良くなることができました。
皆さまも取引先や部下との距離を蕎麦談義で縮めてみてはいかがでしょうか。もちろん、うどんでもラーメンでもカツ丼でも構いません。