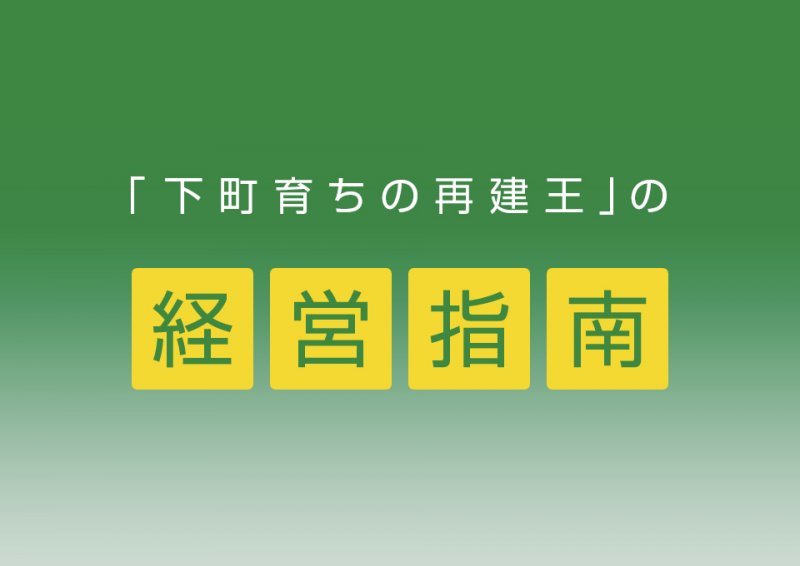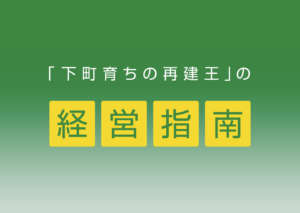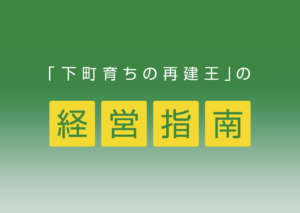人は意識して行動を変えないといけない時があります。部下に対しての不満、社内の不調和、人との摩擦は、もしかすると、あなたが行動を変えることで改善できるかもしれません。
私は40歳の頃、ある人から〝怒りを消すこと〟を教えられました。若い頃の私は、いいかげんな仕事ぶりの人に怒ってばかりいて、怖がられていました。私は東京下町の職人のせがれで短気なので、怒るとつい荒っぽい言葉が出てしまいます。同世代のビートたけしさんも東京下町育ちで有名ですが、「バカヤロー」は下町の接続詞だと言っています。私の親父はくしゃみをするたびに「ハクション!バカヤロー」と大声を発していました。
そんな私が、怒りが湧く瞬間、〝意識を怒りに任せずに、まずその結果や原因を考える〟という習慣を身に付けました。ミスをした部下に「バカヤロー、何やってるんだ」と言う前に、「なぜこうなったの?」「それでお客さまは何て言ってる?」と確認すると、そこに意識が向くので、怒りをスルーできるのです。
それまでの私は〝怒る〟と〝叱る〟の区別がありませんでした。怒った後に何を教えても、相手は萎縮しているので教育的指導になりません。それが怒らなくなったことで、叱るという俯瞰(ふかん)の目線を持てたのです。中途入社でありながら、仲間に支えられて業績を伸ばし続けられた背景には、自分のこの変化が大きかったと思います。怒りに身を任せることは、昨今ではパワハラにつながりかねませんので、ますます注意が必要です。
米国の哲学者で心理学者のウィリアム・ジェームズは「心が変われば行動が変わる 行動が変われば習慣が変わる 習慣が変われば人格が変わる 人格が変われば運命が変わる」と言っています。ここで私が申し上げたいのは、トップの行動が変わると、社運が変わるということです。激動の時代に、これまでの仕事を続けるだけで会社は守れますか? 歴史ある会社はどこも、時代に合わせて上手に変化を遂げてきています。容易ではなくとも、柔軟に新しいことに取り組まないと、5年後、10年後が危ういのです。
「困難だからやろうとしないのではない、やろうとしないから困難なのだ」とは、古代ローマの哲学者セネカの言葉です。哲学者たちはこういった論法を好むようで、前出のウィリアム・ジェームズも「苦しいから逃げるのではない。逃げるから苦しくなるのだ」という言葉を残しています。また、『幸福論』で知られるフランスの哲学者アランは「笑うのは幸福だからではない。むしろ、笑うから幸福なのだ」と言っています。
これらの言葉を参考に、トップ自ら行動を変え、笑いながら社運を上げてゆきましょう。