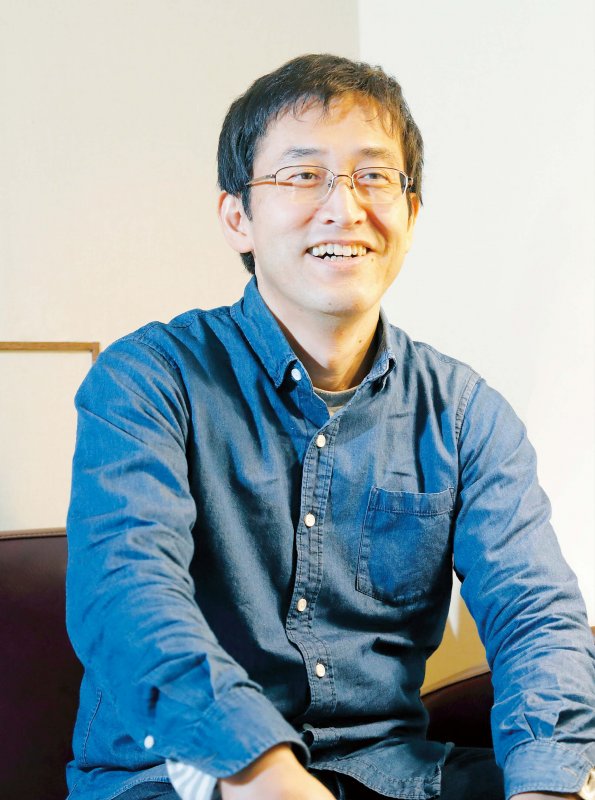5歳でホラー漫画に目覚める
「トップ・ホラー漫画家が太宰治の『人間失格』を独自の解釈で捌く!」。そんなニュースが、この春、出版業界をにぎわせた。
掲載先は、『ビッグコミックオリジナル』(小学館)。30年間ホラー一筋でやってきた漫画家が、ホラーの手法を使って不朽の名作をまったく新しい世界観でよみがえらせたことで評判を呼んでいる。 「『人間失格』は人の業というものの恐ろしさを描いた“対人恐怖の物語”です。ホラーを描くものとして、表現する余地があるなと感じました。それと、主人公の大庭葉蔵が女性にモテること以外は自分そっくりで大変驚きまして。主人公に共感できると描きやすいので、これはいけると思いました」
そう話す、伊藤潤二さん。目の前で優しくほほ笑む癒やし系の紳士が、あのようなおどろおどろしい作品を描くのだろうか。こちらの心の内を察してか、伊藤さんは低く穏やかな声で語り始めた。 「ホラー漫画と出会ったのは5歳のときでした。姉が愛読していた少女漫画誌に掲載される楳図かずお作品のファンになったのがきっかけです。以来、同世代の少年らが熱狂するようなスポ根漫画には目もくれず、ホラー一筋になりました」 小学生になると読むだけじゃ物足りず、わら半紙にコマ(枠)を描きホラー漫画やギャグ漫画を友人らと描くようになったが、漫画家になれるとは夢にも思っていなかった。父親が会社員だったため、自分も堅実な道を歩むのだろうと思い込んでいたからだ。
高校卒業後は「ものづくりが好きで手先が器用」などの理由で、歯科技工士の道に進んだ。ところが義歯をつくりながら、つい漫画の構想を練ってしまう。そんな中、朝日ソノラマ(現・朝日新聞出版)の『月刊ハロウィン』で新人漫画賞「楳図かずお賞」が創設されることを知った。
「敬愛する楳図先生に作品を読んでもらう絶好のチャンスだ!」
そう期待して、休日を返上して短編30ページの『富江』を締め切りギリギリで描き上げた。漫画をエンディングまで描き切ったのはこれが初めてのことだった。ここから伊藤さんの人生が動き始める。審査員の一人である楳図かずお氏が『富江』を「ホラー心がある作品だ」と高く評価し、同作は佳作を受賞したのだ。
頼りになるのは自分の腕のみ
伊藤さんは手堅い。漫画家デビューが決まったからといって歯科技工士を辞めることはせず、しばらく二足のわらじを履いた。しかし、徐々に漫画の仕事が増え、睡眠不足になるに連れ、限界を感じるようになった。そのため3年後に独立を決断。「バイトをしてでも漫画一本でやっていくつもりです」。思いの丈を担当編集者にぶつけたところ、「じゃあ、連載をあげる」と意外にもあっさりと声を掛けてもらった。26歳のことだった。
チャンスをくれたのは伊藤さんの最初の担当編集者である朝日ソノラマの故・原田利康氏。楳図かずお氏、高橋葉介氏らの売れっ子漫画家の担当を務めた敏腕編集者だ。「素人同然の私をプロの漫画家に育ててくれた恩人です。見せ方の基礎やテンポ、ストーリーにおいても原田さんからインスピレーションをもらいました」
ひとまず『月刊ハロウィン』で短編を描く一方で、『富江』の連載も手掛けたが、どうしたことか描けば描くほど人気が下がってしまう。「ショックでしたけど、なにくそという気持ちの方が強かった」。伊藤さんは、連載していた『富江』を一時中断すると決め、別の読み切りを描き始めた。それから4年後のこと。代表作の一つとなった『首吊り気球』(平成6年)を皮切りにヒット作を連発するようになる。
「当時はこれを描いたら死んでもいいという気概で筆を走らせていました。20代から30代前半は肉体的にも若く、踏ん張りが利く時期ですから、漫画家人生でもっとも充実していたと言えるでしょう」と伊藤さんは当時を振り返る。伊藤潤二作品といえば、画力が魅力だ。作品全体に漂う不気味な世界観は、細部にまでこだわり抜いた繊細な「線」で表現されている。
「絵の密度がスカスカなのがどうしても許せないんです。ベタ塗りに頼るのではなく、線を重ねて全体を暗くするのが私なりのこだわり。締め切りの都合で書き込みが足りなければ、単行本になる直前に納得できるまで加筆しています」
1コマに2時間以上費やすこともあるという書き込みの緻密さは同業者も舌を巻くほどだ。何度バラバラ死体にされても再生増殖する美女・富江。自然も街も人の体もすべてがぐるぐると渦を巻いてしまうグロテスクな描写。ともすれば「ギャグ漫画」と取られかねない奇抜な発想でありながら妙にリアルなのは、人体図鑑を片手に描かれる画力によるものだろう。
伊藤さんはデビュー以来、たった一人で原稿に向かい続ける。常駐のアシスタントはつけない。トーン貼りやベタ塗りなどの単純作業はかつて母親や姉に依頼していたというが、現在は絵本作家の妻の友人に手伝ってもらう程度だ。
2年前からは作業効率を考えてフルデジタルに移行したという。 「ネームという絵コンテは細かすぎて一度手描きで描き終えると修正したくなくなるのですが、デジタルに変えてからは修正作業をいとわなくなりました」
修正をいとわない理由がもう一つある。仕事の転機となった『憂国のラスプーチン』(22年)は、伊藤さんが初めて社会派漫画に挑み、良い意味でファンの期待を裏切った作品だ。原作は作家の佐藤優、シナリオは長崎尚志というビッグ・ネームとタッグを組んだ。
「長崎尚志さんは原稿が早く、百戦錬磨のヒットメーカーです。合作は初めての経験でしたので学ぶことが非常に多かった。特に感銘を受けたのはエンディングです。それまでの私は、細部にこだわりすぎて、終盤に差し掛かるにつれてページが足りなくなって困る、といったことをしがちだったのですが、長崎さんと出会って、起承転結に近い形で構想を熟考し、修正を重ねるようになりました」
未知なる発想を目指して
未来について尋ねると、「許されるものなら社会と隔たってひたすら描き続けたい」と言う。誰にも邪魔されず極限まで作品に集中すれば、自分の想像をはるかに超える作品を生み出せるかもしれない。「でも……、作品の出来不出来についてはあまり悩まないようにしています。時には割り切りも必要ですからね」と付け加える。
インタビューが終わったころには、すっかり日が落ちていた。これからどうされるんですかと尋ねると、「まだまだ描きたいことがあるので仕事場に戻りますよ」と少年のような表情を見せた。伊藤さんの夢は今も昔もたった一つ。
「今まで誰も見たことがないような世界を描き、読者を震え上がらせること」だという。
伊藤 潤二(いとう・じゅんじ)
ホラー漫画家
昭和38年、岐阜県中津川市生まれ。61年、ホラー漫画月刊誌『ハロウィン』の「楳図かずお賞」において、『富江』が佳作に入選し同作でデビュー。代表作に『富江』『道のない街』『うずまき』『首吊り気球』など。平成21年、愛猫と妻との日常を描いた実話エッセイコミック『伊藤潤二の猫日記 よん&むー』を発表し、内容がギャグ漫画であったことからファンを大変驚かせた
写真・後藤さくら