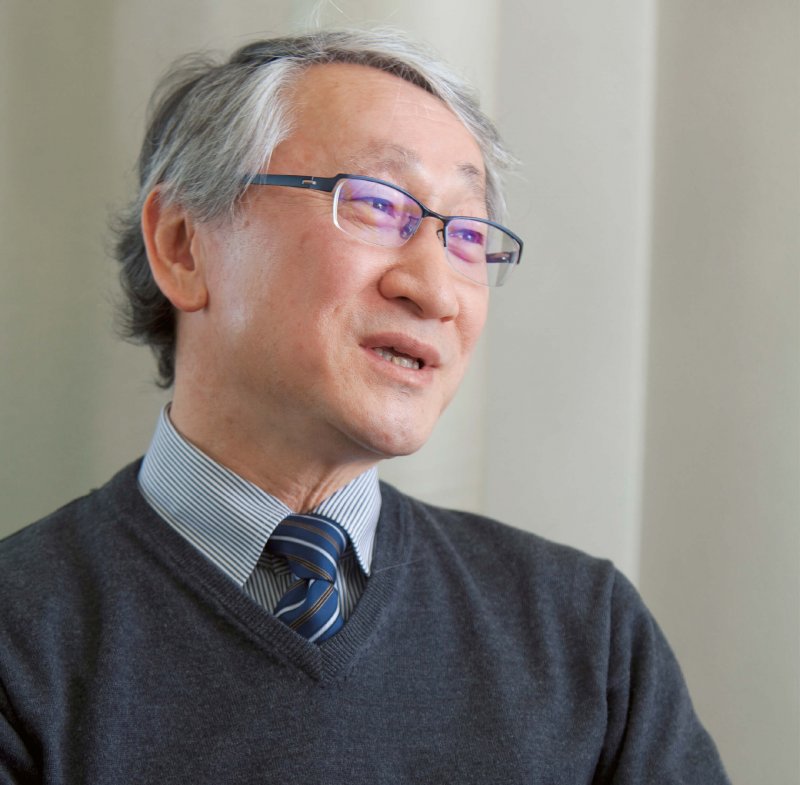〝世界初〟の試みは素晴らしい。まだ見ぬ世界への扉を開く挑戦というのは、その言葉を聞くだけでも期待に胸がときめくものだ。平成22年、世界で初めて小惑星から表面物質を持ち帰ることに成功した探査機『はやぶさ』。このプロジェクトマネジャーを務めていたのが川口淳一郎さんだ。丁寧に紡がれる言葉は門外漢にも非常に分かりやすく、経験に裏打ちされた説得力のあるものだった。
時には後進に道を譲ることも必要
昨年12月3日、種子島宇宙センターから小惑星探査機『はやぶさ2』が打ち上げられたことは、記憶に新しい。『はやぶさ』の後継機としてJAXA(宇宙航空研究開発機構)で開発された『はやぶさ2』は、初代同様、小惑星への着陸およびサンプルリターンが計画されている。
川口さんはこの『はやぶさ2』プロジェクトに、アドバイザーという立場で参加している。「私は『はやぶさ』でプロジェクトマネジャーを務めました。この『はやぶさ2』も、言ってみれば私が立ち上げようと努力してきたものです。ただ、プロジェクトを立ち上げようと努力をすることと、実際に行うということはイコールではないときもあります」。
穏やかな笑顔でそう語る川口さんは経験も実績も豊富な科学者である。それにもかかわらず、今回は最前線での実務から一歩引いた。これには理由がある。川口さんはこう話す。
「私が『はやぶさ』に携わったのは、40歳のころです。もちろんチームには年配の方もいらっしゃいましたが、主力は30代以下が多かった。やはり新しいプロジェクトは未来のあるそういう年代でやるべきだ、というのが持論なんです」
宇宙開発のプロジェクトは総じて期間が長い。短いものでも、プロジェクトのスタートから機器を設計、製作して打ち上げるまでに4年はかかるという。はやぶさの場合は、新規技術が必要だったこともあり7年を要した。そして、4年の飛行予定が、予想外のアクシデントにより7年に延びた。その結果、足かけ15年という長期プロジェクトとなったのだ。
川口さんは、平成27年で60歳を迎える。仮に今、プロジェクトに関わっても、定年退職のために道半ばで去らなければならない可能性もある。それも一歩引いた立場でプロジェクトに携わることにした理由の一つだ。
「宇宙開発は、私一人がやっているわけではないので。『はやぶさ』も『はやぶさ2』も自分でできれば、それは非常にやりがいのある素晴らしい経験になるでしょう。でも、それを独占していいわけじゃない。携わる人がたくさんいて、このような活動は進んでいくのです。そう考えるべきですよね」
これは、どの仕事にも当てはまる。全体の成功を願うならば、自分が経験するだけではなく、時には後進にチャンスを譲ることも大切なのだ。
守ろうと思うと発想が乏しくなる
では、後進の育成という面で、具体的にどのようなことが大切なのか。川口さんは〝親方徒弟〟の関係が、日本人には適しているのではないかと言う。
「先輩の背中を見て育つというと、ちょっと浪花節みたいな感じかもしれないけれど(笑)、結局、大切なのは現場を通じた共同作業だと思います。たとえば会社の創業者が、精密なマニュアルをつくって『これを読んでおけ』と二代目社長に言う。でもこれだけでは伝わりきらないのです。それは上司と部下の関係でも同じです。共同しなくてはダメ。ビジネスを進めていく上で、一体どのタイミングで、何をすべきなのか? 〝親方〟はそれを伝えなければならないし、〝弟子〟は盗まなければならないのです」
そして、このとき伝承しなければならないこと。それは細かな知識や技術ではない、と川口さんは言う。伝承すべき大切なポイントは、次へと前進を図るための決断、そのタイミングだという。
「特に経営者に求められること、それはdecision(決断)です。例えば決断の場面になり、選択肢が二つあったとします。そして、そのどちらがよりリスクの低い選択なのかで悩んでいたとします。でも、本当にリスキーなことは、ここでハイリスクな選択肢を選んでしまうことではなく、悩んで決断のタイミングを逃してしまうことなのです。あるタイミングで、たとえリスクがあっても決断しなければならない。そしてそれは、経験なくして身につけられるものではないし、紙で書いて伝わるものでもないのです」
宇宙開発の世界でも、やはり決断は延期できない。特に惑星に向かって飛んでいく『はやぶさ』などの探査機は、地球の周りを回る人工衛星とは異なり、あるときに必ず何かをしなくてはいけないのだという。そのタイミングが、期限付きでやってくる。人工衛星ならば、地球に落ちてくるわけではないし、どこかへ飛んでいってしまうわけでもない。だが、探査機はそうはいかない。一つのミスでどこに飛んでいくか予測できないのだ。だから、〝ここぞ〟のタイミングを、決して逃すことはできないわけだ。
「期限付きで決断しなくちゃいけないことって、仕事の中でも必ずありますよね。なかなか、完璧な結論っていうのは出ない場合が多い。だいたいが不完全なんです。あと2、3年やれば完璧になるかもしれない……でもそんなの待ってられないわけですよね」
川口さんは何度も自分で決断を繰り返してきた。だからこそ実感が込められた言葉である。そしてこうも付け加えた。「本当は、悩むくらいの選択肢だったら、どっちでも良いんです。どっちでも良いというのはいい加減な判断という意味ではなく、どちらもほとんど差がない。そう考えて、思い切って前進していくべきだと思います。私も先輩から学びました」。
先達が培ってきたものを伝承する。それは非常に大切なことだ。一方で、その中で間違ってしまいがちなのが〝型の内側だけで生きてしまう〟ということだ。
「先輩たちが築いてくれた素晴らしい伝統。この伝統を汚さないように、誇りとして継続しようというのは、実は間違いなんです。それは出来上がった型の内側でしか生きていない、という意味で。素晴らしいから守ろう、そう思った瞬間に、大きく前進できるかもしれない型破りな発想はできなくなってしまいます」
出口が見えないからこそ挑む意味がある
「宇宙開発は予算の確保が難しいのです。先行きが不透明な部分もあります。そんなとき、プロジェクトに関して『何が成果なのか事前にはっきり見えるようにしろ』と求められることがあります。出口戦略というんでしょうか。でも、例えば〝この望遠鏡をつくったら何が見えるか言ってみろ〟だなんて、最初から言えるならつくる必要はないですよね? いつか、宇宙開発で得た技術が社会で転用されたとき、それは〝社会に役立たせるためにつくられたわけじゃない。開発する中で、たまたま社会に生きる技術が生まれたんだ〟と。そう言いたいですね」
初代の『はやぶさ』は、まさに型破りな存在だった。まだ世界で誰も成し遂げたことがないことを成し遂げるために生まれてきた。もちろん、そのときは出口は見えていない。その意味でいうと、『はやぶさ2』は少し異なる存在だと、川口さんは言う。「『はやぶさ2』によって、『はやぶさ』が伝承できてうれしいと思っているかというと、半分は違う気持ちですね」。
たしかに『はやぶさ2』を打ち上げる機会があったということは、素晴らしいことである。今後も宇宙開発事業が発展していくために、今のコミュニティーやグループを継続していくためにも必要なことだった。しかし、それだけでは不足だと川口さんは考えている。
「初代があつらえたものをやっている、それだけではダメなのです。型は破らなければならない。今携わっているスタッフには、『はやぶさ2』はそのための実力をつける場だと、そう思ってほしいですね」
今回の経験を糧に、もっと型破りなプロジェクトを立ち上げてほしい。川口さんは今後も後進を後押しし、ときに引っ張って歩いていきたいと語る。
「そんな型破りなチャレンジを見た子どもたちが、宇宙に興味を持ち、自分も新しいことにチャレンジしようという勇気を得る、そんな影響を与えられたら宇宙開発事業は、社会を変える一翼を担っていけると思います」と柔和な笑顔を見せてくれた。
川口淳一郎(かわぐち・じゅんいちろう)
宇宙工学者、工学博士
1955年青森県生まれ。京都大学工学部機械工学科を卒業後、東京大学大学院工学系研究科航空学専攻に進学。83年に同博士課程修了。旧文部省宇宙科学研究所に入り、2000年に教授就任。火星探査機『のぞみ』など数々のミッションに携わり、小惑星探査機『はやぶさ』ではプロジェクトマネジャーを務めた。現在、宇宙航空開発機構(JAXA)教授、シニアフェローを務める。著書に『閃く脳の作り方』『「はやぶさ」式思考法』(ともに飛鳥新社)などがある。
写真・金澤篤宏