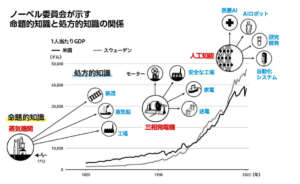ロシアのウクライナ侵攻は衝撃的だった。米中冷戦、コロナ感染、ミャンマーの軍事クーデターなど2018年以降、企業経営を揺さぶる出来事が続いている。筆者は新聞記者時代に中東、ロンドン、北京に駐在し、湾岸戦争や冷戦終結とソ連の崩壊、中国の台頭など世界の激変に立ち会った。激流の中で振り回されるばかりだったが、激しい変化をタフに切り抜ける人や企業がいるのを見て、得た視点が三つある。
第一は「論理的に起き得ることは必ず起きる」。1990年7月末、サダム・フセイン時代のイラクがクウェート国境に戦車を並べたとき、大半の人は「脅し」と考えた。だが、クウェートの軍事力が貧弱で、イラクだけでなくイラン、サウジアラビアなど地域大国との関係が険悪化していたため、侵攻が論理的に起き得ると、対処した人がいた。ビジネスマンは「理屈」を嫌うが、正しい論理と推論こそ客観的な判断の基礎となる。
第二は「指導者の行動には必ず金銭的動機がある」。湾岸戦争直前のイラクは8年超のイラン・イラク戦争のため国家予算の40%を軍事費に充てる国となっていた。軍事費を投資と見れば、最も安易な回収手段は付加価値を持つ他国の侵略。プーチン大統領も大国の威信のために投じてきた莫大(ばくだい)な軍事費を回収するため、肥沃(ひよく)で気候もよく黒海の長い海岸線を持つウクライナにロシア製兵器の威力を示す場が必要だったのかもしれない。
第三は「ファースト・ペンギンになるな」。正しい情勢判断をいち早く下し、工場や資産を処分し、資金を回収し最初に戦場を離脱した会社が生き残る確率は高いはずだが、早過ぎる判断は間違えるリスクも高く、結果に伴うリベンジも最大となる。離脱や見切りでは「先頭集団の後方」か「二番手集団の先頭」が生存確率の高いポジションといえる。つまり「一定の損失を覚悟し、致命的な損失を防ぐ」というスタンス。もちろん三番手、四番手集団は逃げ遅れとなるので絶対に避けなければならない。
この数年、グローバル情勢がこれほど流動化した要因は「中国の劇的台頭」に尽きる。米中の直接的な対立だけでなく、米国の影響力の相対的な低下によって、世界の秩序維持が困難になったためだ。米国を恐れていた独裁的な指導者が利己的行動や力による現状変更に動き出した。これから数十年、こうした不安定な世界が続くだろう。企業経営者は視界不良の中でも成長のために投資を続けていかざるを得ないが、紹介した三つの視点が役立つかもしれない。