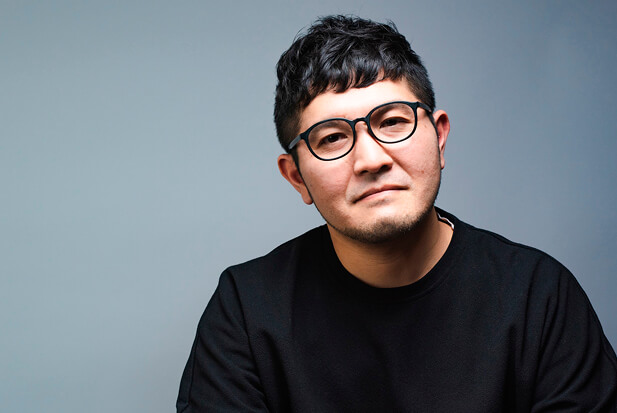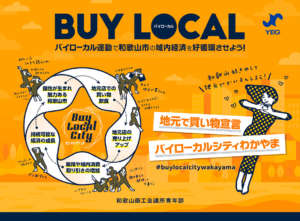七尾YEGは、コロナ禍で打撃を受ける地元観光業や飲食店、雇用面での影響を受けている障がい者を支援したいと「シェフ・障がい者・YEG」三者での共同プロジェクトを立ち上げた。豊かな地産食材を使って製造したソースの販売を通じて、七尾の魅力を全国にPRする。
地域の青年経済人として障がいのある人を支援する
七尾YEGは、ミシュランガイド掲載や国内最大級の料理コンペティションでの入賞経験を持つ3人の地元シェフ、そして就労継続支援B型事業所である「ななお・なかのと就労支援センター」と共同し、ソースを商品化した。この取り組みについて、担当委員長の五十嵐亮さんに伺った。
「七尾YEGでは、障がいのあるお子さまを持つメンバーがいたことをきっかけに、5年ほど前から障がい者を理解し、コミュニケーションを図る取り組みを行っています。このコロナ禍で支援センターの人々の働く場が減っていると聞いて、新しい仕事をつくれないかと考え、このプロジェクトをスタートさせました」
組織力で持続可能なビジネスを創造
能登の豊かな水産物や農産物を生かす商品で、保存性もあり一般的に利用されるものとして着目したのがソース。支援センターの障がい者は商品の生産とパッケージのデザインを担当する。また、本当においしいものをつくりたいとの思いから、地元有名シェフに監修を依頼した。
全国大会の開催を飛躍のチャンスに
石川県連では2024年度にYEG全国大会を開催する予定で、来県する多くのメンバーに商品を届けるため、生産体制の拡張を計画している。
「オール石川でお迎えするこの全国大会を、ソースを通じて能登の地を全国の方に知ってもらうチャンスだと捉えております。まずは24年度を目標として、クラウドファンディングによる資金調達も行いながら、現在年間1000セットの生産能力を5倍にすることを目指し、そしてその後のビジネス展開へとつなげていきたいと思っています」
商品を通じて地域の魅力を全国に伝えたい
3種のソースは、ボトリングやパッケージング、衛生検査も終わり、いよいよ7月上旬に販売開始予定だ。さらに単発の取り組みで終わらせないためのこだわりについて五十嵐さんは言う。
「まずはプレスを通じて各種媒体によるPRをしっかりと行います。その後は地元の観光施設や道の駅での販売はもちろん、都心のアンテナショップやふるさと納税を活用して全国各地へと届けたいと思っています。また、ソースに使われる野菜や果物はもちろん、しょうゆや塩、酢や山椒(さんしょう)に至るまで能登半島の豊かな自然が育んだもの。商品を手に取った方たちにその魅力が伝わり、シェフのレストランや七尾の地に足を運んでくれることを願っています」
と、最後に今後への期待も語ってくれた。
【七尾商工会議所青年部】
会長:尾古 隆史
設立:1986年
会員数:58人
HP:https://m.facebook.com/nanaoyeg/
YEG CONNECT
PROFILE
全国各地で地域の未来のために励むYEGメンバーを紹介するコーナー。6月号は富山YEGの種昻哲さん。富山市を拠点として全国で住宅や店舗、オフィスのデザインを手掛ける傍ら、柔軟な発想で取り組んでいる活動について伺いました。
―若手起業家を支援する富山駅前の施設「スケッチラボ」の立ち上げに関わったとお聞きしています。
2019年度に市への提言を担当したことをきっかけに立ち上げメンバーとして声が掛かり、現在は運営チームとして参加しています。
―提言された内容についてお聞かせください。
20年に富山駅の二つの路面電車の直通運転が始まったとき、沿線を核とした持続可能なまちづくりを目指そうと提言しました。駅前の統合広場を新たなビジネスチャンスを生み出す場とすることや、沿線の空き家・空き店舗を活用したビジネス交流・起業イベントの実施などです。
―自身もオフィスをシェアキッチンとして貸し出していますね。
路面電車沿いの便利な場所にあるので、提言を行った後すぐ実行しました。オフィスを一部開放することで、新しい人の流れをつくりたいと考えています。
―経営者と大学生のみが入店できるバーの運営など、多岐に活躍されていますがさまざまな発想はどこから。
起業する際、富山には面白い仕事はないよ、と言われたことから、ないのなら自分でつくってしまおうと考えたんです。
―最後に今後の活動について聞かせてください。
最初から仕様が決まっているものではなく、プロジェクトやカルチャーを一から作っていく仕事。時間もかかり大変ですが、つくっていくプロセスを楽しみたい。仕事の面では企業をコンセプトから建物まで丸ごとデザインしてみたいですね。
取材・写真撮影 : 日本商工会議所青年部(日本YEG) 広報ブランディング委員会