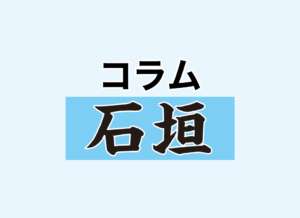ドイツには「シュタットベルケ」といわれる100%自治体出資の公益事業体がある。電力・ガスなどのエネルギー事業から収益を上げ、地域の公共交通や上下水道の赤字を埋め、事業全体では黒字を出している。日本に同様のモデルを導入すべきだという意見はあちこちで聞かれる▼
日本でも近年、出資をして新しい事業を立ち上げる自治体は多い。例えば、再生可能エネルギーや廃棄物リサイクルなどの循環型経済の取り組みだ。しかし、事業の収益性は低く、ドイツのように他の公共サービスの赤字を補填(ほてん)するほどの余裕はない。この背景には、事業体の規模が小さいことや、すでに大手民間企業のシェアが高く参入する余地がないことがある。政府はこれまで電力の自由化を進めてきたが、改めて地域の持続性確保を目的に制度を見直すべきだ▼
また、これまでも自治体は観光事業や地域開発などに出資や融資を行い、公的なサービスの提供を支援してきた。これら第三セクターと呼ばれる組織は赤字まみれという印象が拭えないが、先日公表された経営報告書によると、情報通信や住宅都市サービスでは7~8割程度の事業体で黒字を計上している。デジタル化が進展し生活環境が大きく変わる中で、公共性が高く、かつ収益を上げられる事業は多様化していくはずだ。エネルギー産業に限らず新たな有望産業を探して、そこでの収益を他の公共サービス提供に流用することが有効だ▼
今後、人口減少が続けば行政サービスの維持が困難となる。それを回避するには、今すぐ地域の持続性確保の観点から制度を見直すとともに、自治体の事業を多様化させるための大胆な仕組みづくりに取り組まなければならない
(NIRA総合研究開発機構理事・神田玲子)