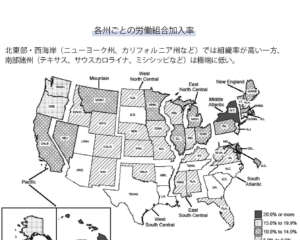定年年齢の見直しなどにより、中高年労働者の割合が高まっている。年齢が高くなれば体力は低下し、近年、企業の現場では“行動災害”が増えている。そこで、何かと忙しくなる年末を控えて、中高年労働者を守る「安全体力®」の提唱者である乍智之さんに具体的な予防策を聞いた。
乍 智之(ながら・ともゆき)
JFEスチール株式会社西日本製鉄所(倉敷地区)|安全健康室ヘルスサポートセンター主任部員(係長)|公益財団法人日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー
転倒や腰痛など行動災害の削減に寄与する「安全体力Ⓡ」
―行動災害とは聞き慣れない言葉ですが、どのようなものですか。
乍智之さん(以下、乍)労働行政の現場で近年注目されている、転倒や腰痛などの、「作業行動に起因する労働災害」のことです。安全装置の設置義務化などにより、挟まれや巻き込まれ、墜落などといった命に関わる労働災害は減少していますが、近年は設備装置面だけでは対策のしようがない行動災害が増えています。高齢になると、平らな地面でも体力がない人は転びますからね。
―労災の範囲なら企業にとっては大問題ですね。
乍 高齢者の転倒は、高確率で骨折に直結します。最近は若年世代の体力も低下傾向にあり、2021年度の転倒災害による休業期間は全世代平均で47日です。65歳以上に限ると2カ月超。JFEスチールの場合、取り組み開始前のピークだった04年時点で、筋骨格系疾患による社員の休業日数を休業損失金額に換算した額が年間2575万円もありました。「安全体力®」の取り組みを始めてからは休業件数も日数も減り、損失額も22年は380万円まで低下しています。
―行動災害が特に増えている業種があれば挙げてください。
乍 社会福祉施設や小売業など、第三次産業の現場で増えています。私どものような製造業は「ご安全に!」というあいさつに象徴される通り、もともと安全意識が高いのですが、今はそういった、必ずしも安全意識が高くなかった業種で行動災害が増えています。早急に対処すべきだと思います。
─「安全体力®」とは、どのようなものでしょうか。
乍 「安全に、長く、元気で働くための体力」です。発案当初は「当所(JFEスチール社)で安全に働くための体力」としていましたが、広く社内外の労働者全体に通用する考え方だと気付き、定義し直しました。
―労働者全体に通用するとは、具体的にはどういうことでしょう。
乍 日本は今、どの産業分野も労働者の平均年齢が上がっています。若年人口が減少し、企業は、これまで活用してこなかった女性や高齢者の労働力に頼らざるを得ない状況なのです。それを受けて、国も定年年齢を段階的に引き上げるなど、高齢者が働きやすくなる法整備を続けています。今後はもっと労働者全体の高年齢化が進みますが、そうすると問題になってくるのが、加齢に伴う体力の低下による行動災害の増加です。「安全体力®」は、行動災害を減らすことに役立つ点で、労働者全体に通用する考え方なのです。
独自の機能テストと体操を労働現場の実態に即して考案
―どのような経緯で行動災害の視点を得たのですか。
乍 03年に川崎製鉄とNKKが統合してJFEスチールになった当時、社員の腰痛と転倒がとにかく多かったのです。それである日、傾斜地での作業中に転んで大きなけがをする事故が起きた際に、「そもそもこの人の体力はどうだった?」と考えたんですね。というのも、私が専門としてきたスポーツの世界では、けがやミスが起きるのは本人の体力がなかったか体の使い方が間違っていたせいであり、環境のせいにはしません。長らくその文化で育ちましたし、そもそもアスレティックトレーナーですから、自然に体力に目が行ったのだと思います。
―労働者に「安全体力®」を身に付けてもらうため、「安全体力®」機能テストと「アクティブ体操®」のセットが有効なのですか。
乍 そうです。「安全体力®」機能テストは「安全体力®」を“見える化”するもので、転倒リスク、腰痛リスク、ハンドリングミスの各テストから成ります。転倒リスクテストでは5mバランス歩行、40㎝の台からの片脚立ち上がり、2ステップ幅測定を行います。バランス歩行は、体の前にA3の画板を持ってもらい、水を半分入れたペットボトルを載せて、長さ5m・幅10㎝、高さ5㎝の平均台を渡るタイムを測ります。2ステップテストは一般的にはスタート時の爪先から2歩目の爪先の測定ですが、当所では2歩目はかかとの位置で距離を測定します。物をまたぐ、越えるなどを想定しているからです。また着地はつまずきのリスクが高くなる、爪先からの着地ではなく、かかとからの着地になっているかも確認します。
―労働現場の実態に即した内容になっているわけですね。
乍 その点は非常に意識しました。バランス歩行で画板を持つのも、視界を全く遮られないまま移動できる場面は実際の仕事では少ないからです。段ボール箱を抱えていたり、道工具で両手がふさがっていたりしますよね。そんな状態でも体幹を制御して安全に歩けるかどうかを評価したいのです。
―「アクティブ体操®」についても教えてください。
乍 「アクティブ体操®」part1は、筋骨格系疾患を減らす目的で04年につくりました。製鉄所内の65の職場における業務の動きを分析し、最終的に「筋出力の高い作業」「移動の多い作業」「拘束性の高い作業」の三つに整理し、どれに関しても不良姿勢が改善される内容にしています。ですから、腰痛に限らず、デスクワークの人の肩凝りや五十肩の改善にも使えます。
―「アクティブ体操®」はpart2もありますね。
乍 part2は09年につくりました。1と違って狙いを転倒災害予防に振り切ったので、スカートの女性ではできなかった両足を横に広げる動きも入れました。現代人は畳に座らなくなったり和式トイレがなくなったりして、足首も膝も股関節も弱く、また固まりやすくなっています。part2では股関節を中心に筋力・柔軟性・バランスを改善できます。
―実際にこう改善されたというデータがあればご紹介ください。
乍 筋骨格系疾患の部位別発生件数率の推移を示したグラフがあります(28ページ)。最も多かった腰痛で休む人が顕著に減っています。連動して、前述の休業損失金額も低下しました。
日本の未来のため若年世代の体力強化も必須
―「最近は若年世代の体力も低下傾向」との話もありました。どういった点にそれを感じますか。
乍 「安全体力®」機能テストの結果を毎年集計しているのですが、10年の20~30代に比べて、(10年後の)20年の同年代は、純粋な筋力を測る握力や片脚立ちの数値も、移動能力を測るバランス歩行や2ステップテストの数値も、両方悪くなっています。スマホやゲームの存在や、生活の中で“しゃがむ”動きがほぼゼロの世代だから当然ではあるのですが、このままいくと、彼らが高齢になってからの行動災害の発生率は今の60代、70代の比ではないと思います。
―定年年齢の延長が国の方針であることと照らし合わせると、恐ろしいですね。企業レベルで損失が増えるだけでなく、社会保険行政も圧迫しかねない。
乍 ですから、今のうちから手を打たないといけません。当所では入社時の「安全体力®」機能テストが一定水準を下回った場合、2カ月の研修期間中の運動訓練によって全て改善し、十分な「安全体力®」を獲得した上で配属しています。
―御社の公式YouTubeチャンネルには「アクティブ体操®」の動画が投稿されています。
乍 特にpart2は、正しく行えばアスリート用にも使えるくらい負荷があります。最初は「こんなハードな体操できないよ」とおっしゃる企業もありますが、きちんと続けていれば必ずできるようになります。逆に言うと、取り入れただけで実はやっていない企業と継続されている企業では雲泥の差がつきます。社員の皆さんに「安全に、長く、元気で」働いてもらいたい企業はぜひ、まずは片脚立ちとpart1のスクワットだけからでも、始めていただけたらうれしいですね。
「アクティブ体操®」HPはこちら▶https://www.youtube.com/watch?v=KPxt7vyQ6Zo