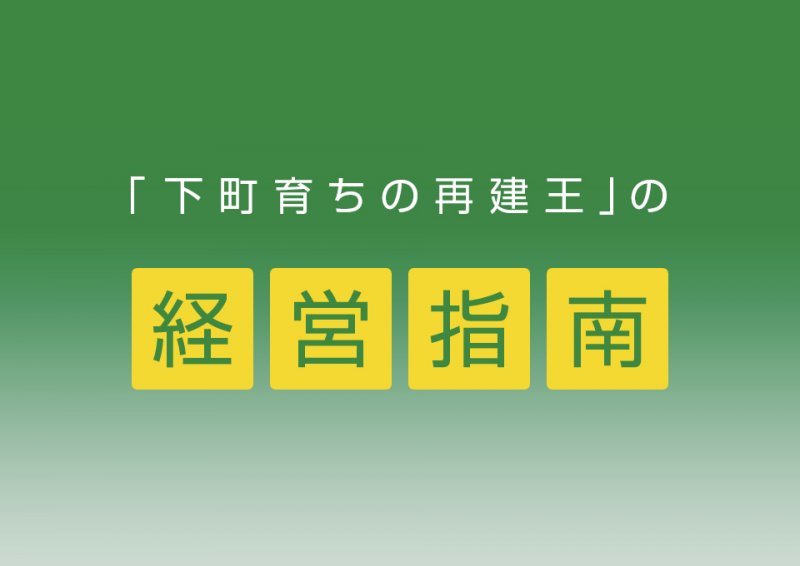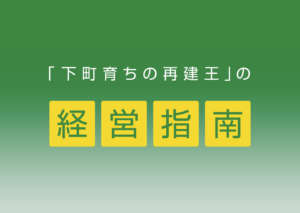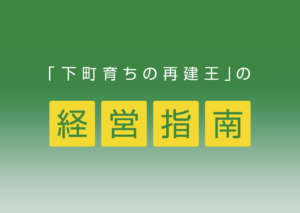室町時代の能楽の大成者、世阿弥が『花鏡(かきょう)』奥段に記した「初心不可忘」(初心忘るべからず)という言葉は、600年を経た今でも、私たちの生活の場で用いられています。
ご存じのとおり、「何事も、始めた頃の謙虚で真摯(しんし)な気持ちを忘れてはならない」という意味ですが、世阿弥は万事の神髄として、「是非初心不可忘」(是非の初心忘るべからず)、「時々初心不可忘」(時々の初心忘るべからず)、「老後初心不可忘」(老後の初心忘るべからず)と三つの初心を説いています。
一つ目は先ほどの意味。次は上達することにより見える景色が変わったら、その時その時を初心と感じて精進を重ね続ける事。そして最後、老後の初心は、老齢となれば今までの鍛錬とは異なり、老いによって知る新たな境地の中で、派手な動きで演じなくても成し得る至上の形の追求こそが、求められる唯一の姿である、ということのようです。
凡人には到底至らない境地であり、恐るべき探求心に感服するばかりです。私は、この言葉にさらに別の意味をくみ取り、若い頃からずっと使ってきました。
例えば、歌舞伎を愛するファンは、衣装、指先の表現、表情の決め方など、初心者には分からない部分にも演目の面白さや演者の表現力を見いだしますが、それは一部のマニアだけです。芸事を発展させようと考える立場の人は、一般の方への人気拡大が大事です。初めての人でも理解しやすく、ファンになるような仕事をしなければ、芸事が先細りになりかねません。ですから、どれほどレベルの高い芸を見せる場であっても、初めての観客をも感動させなければならない、という自分への戒めがあったと思います。
ですから世阿弥は、自らに厳しく成長を目指すと同時に、初心者が見ていることを意識してその心をつかむ事を忘れるな、そう言いたかったのでは、と思うのです。そう考えるとそれまでの意味以上に、私たちの仕事に役立つ言葉となります。
どのような商売でも、常連さんが来店するとその方を喜ばせようとします。しかしそこに一見のお客さまがいたら、自分は場違いな場所に来た、そんな気分になるものです。そう感じさせないように、おなじみさんと同じ温度でにこやかにあいさつをする。初めてでも自分の来店が喜ばれていると、そのお客さまに感じてもらえる接客、心配りを忘れない事、これは商売が末広がりに繁盛する秘訣(ひけつ)です。
私はこれまで、「初心忘るべからず」という言葉を、初めてのお客さまの気持ちになって店のサービスや接客を考えよう、という意味で度々使ってきました。皆さまのご商売の参考になれば幸いです。