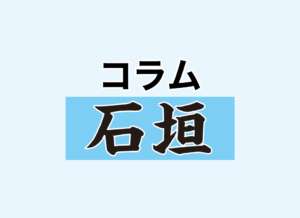6月13日、午前3時過ぎにイスラエルのネタニヤフ首相はイランの核施設の破壊と体制転覆を意図して、200機以上の戦闘機を繰り出し、イランのナタンズやフォルドゥの核施設など100カ所以上を爆撃した。その際、イランの精鋭部隊である「革命防衛隊」のトップのサラミ司令官ら軍幹部やアバシ元原子力庁長官を含む6人の科学者を爆殺した。このイスラエルの攻撃に対してイランは即日100機以上のドローンやミサイルを発射してイスラエルに対し報復した▼
イランは、5月の国際原子力機関(IAEA)の報告書によれば、ウラン235の濃縮度60%の貯蔵量を2月から1・5倍に増やした。この量は核弾頭9発分に相当する量である。一般的に、武力攻撃を受けた場合の自衛権の行使として武力反撃することは認められている。しかし、単にイランの核開発が脅威だからといって、ネタニヤフ首相が自衛権の行使として先制攻撃をすることには疑問が残る▼
国連の安全保障理事会は両国に即時無条件の停戦決議案を提案した。しかし、米国の拒否権の行使によって流れた。イランもイスラエルもこの戦争がお互いにエスカレートして泥沼の戦いになることは避けたい意向である。6月の16、17日にカナダ西部のカナナスキスで主要7カ国首脳会議(G7サミット)が開かれ、同会議はイスラエルとイラン双方に緊張緩和を求めた▼
日本は原油輸入の9割超を中東に依存しており、その大半がイラン沖のホルムズ海峡を通過してきている。国内には約240日分の石油備蓄があり、すぐに石油流通が途絶える恐れはない。しかしながら、一刻も早くこの緊迫化した両国の関係の安定化が望まれる
(政治経済社会研究所代表・中山文麿)
※6月19日執筆