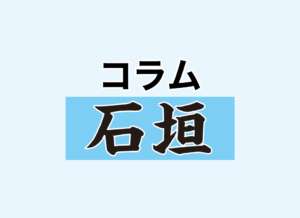中国というのは不思議な国である。長い歴史で中国という「国」が存在したことはない。あったのは秦や漢、唐や明という王朝である。天命を失った王朝が滅びると、乱世からふたたび天下統一を果たした「王家」が国のサイズまで膨らんで王朝を建国する。この繰り返しが易姓革命という中国の歴史である▼
たとえば英仏なら王朝が替わっても国名は変わらない。だが中国では、隋から唐、明から清に王朝が交代すれば別の国になる。それでも変わらないものに名前がないのは、そこが世界の中心と自負しているからだ。これを中華思想という▼
その世界観はこうだ。中心の「中華」という文明が、周囲の東夷(とうい)、西戎(せいじゅう)、南蛮(なんばん)、北狄(ほくてき)という、文明を持たない夷狄(いてき)に囲まれる。匈奴(きょうど)、鮮卑(せんぴ)、柔然(じゅうぜん)、突厥(とっくつ)、契丹(きったん)、蒙古(もうこ)、女真(じょしん)などという、大陸を跋扈するエキゾチックな遊牧民。日本も東夷の一つである▼
50以上の民族を抱える中華人民共和国を主導するのは漢族とされる。だが漢族イコール中華なのではない。多様なものを取り込みながら形成されてきたのが中華である。気が付けば中華の一部、という怖さが中華の本質である▼
中華文明は周囲を飲み込んで膨脹してゆく。唐は鮮卑、元は蒙古、清は女真族によって建国されたが、滅びたあとはみな中華に同化・吸収された。最後の清王朝を辛亥革命で倒した孫文の中華民国は王朝の基盤を築けなかったが、中華人民共和国は毛沢東が建国した王朝とも言える。昭和の日中戦争にもし日本が勝っていたら、数百年後には日本も中華の一部になっていただろう。
(コラムニスト・宇津井輝史)