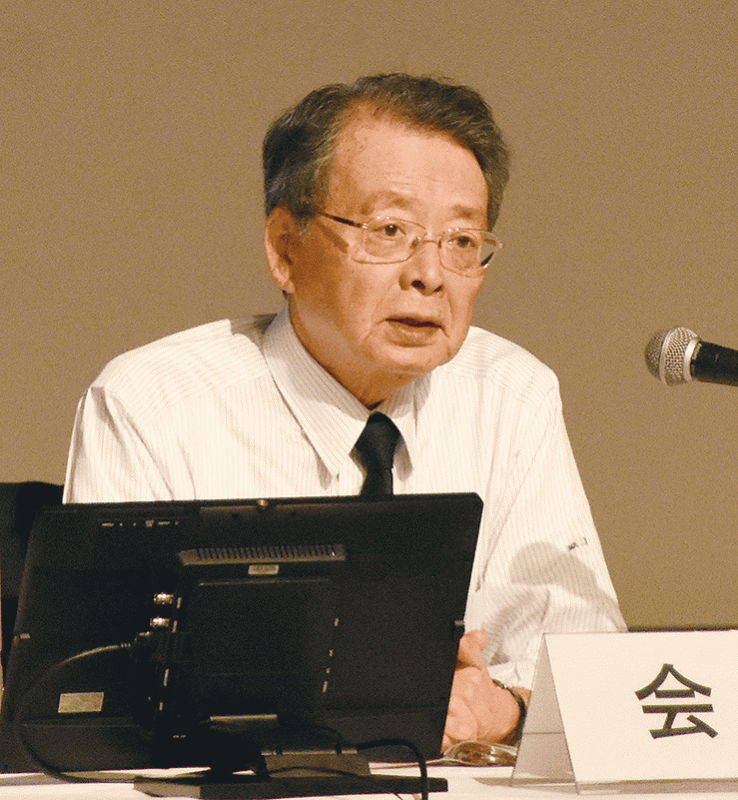日本商工会議所は7月16日、重要政策課題などを話し合う夏季政策懇談会を都内で開催した。会合には、日商の小林健会頭をはじめ、副会頭、特別顧問、常議員・議員、各委員会委員長、専門委員長など60人が出席したほか、全国の商工会議所からオブザーバーとして209人が参加。「成長型経済への移行に向けた『中小企業』と『地方創生』」を全体テーマに活発な討議を行った。
小林会頭は冒頭のあいさつで、「わが国経済を『成長型経済』へ転換していくためには、官民が連携して潜在成長率を底上げする取り組みが不可欠」と指摘するとともに、「中小企業」と「地方」への支援強化が極めて重要との認識を強調。「中小企業と地方の重要性が高まる中で、商工会議所が果たすべき役割もより一層大きくなっている」と述べ、現場の視点に立った議論を呼び掛けた。
会合は2部構成で開催。第1部では「米国関税措置への対応」「中小企業の『稼ぐ力』の強化」「公民共創による地方創生の実現」の三つの視点で討議を行った。第2部では、三つの分科会に分かれて「商工会議所の活動・機能強化」をテーマに、地域総合経済団体である商工会議所に求められる役割や、商工会議所自身の活動強化などについて、先進的な取り組み事例を踏まえながら自由討議を行った。
第1部では、米国関税への対応について、「発注先から中小企業に対して、コスト負担や価格引き下げ要請がなされないよう政府に対する働き掛けが重要」「国際情勢が不安定になる中、中小企業が多角化、新分野への進出、販路開拓などに取り組むための支援策の強化も重要」といった意見が出された。
生成AIの活用については、「さまざまな課題はあるが、人手不足や業務効率化に向けて有効。経営者の関心も高くなっている」「小規模企業では、生成AI導入に向けた人的・資金的余裕がない。補助金の拡大、人材育成支援など後押しが必要」といった意見があった。
サプライチェーン全体での価格転嫁の実現に向けては、パートナーシップ構築宣言の実効性を向上させる必要性を指摘する意見のほか、「医療・介護など制度的に価格転嫁ができない業種についても目を向け、課題解決を行っていくことも必要ではないか」との声が寄せられた。
投資を呼び込むための地域づくりについては、「企業の投資意欲は高いが、港湾整備をはじめ、インフラ整備が遅れている。新たな需要を生み出す『未来への投資』としてのインフラ整備がなければ、日本経済は成長できない」との指摘があった。
地域資源を活用した広域連携による観光地域づくりに向けては、「国内観光需要がしぼみ始めているため、地域資源をお金に変える取り組みのほか、サービスの質的向上、周遊・回遊といった視点から、需要を喚起することが必要」などの意見があった。