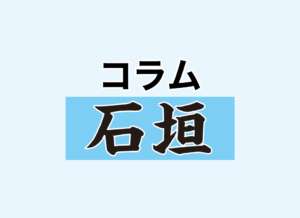最近のAIの進歩は目覚ましく、ビジネスや社会に大きな影響を与えている。AIの前身となる電子計算機の開発には、英国のアラン・チューリングとハンガリー出身のジョン・フォン・ノイマンの貢献が大きい。第2次世界大戦中、チューリングはドイツ軍の暗号機エニグマを解読し、Uボートの動きを把握することで戦局を有利に導いた。一方、ノイマンは原爆開発の爆縮計算を行い、さらに現代のコンピューターの基本構造(ノイマン型アーキテクチャ)を提唱した▼
最初の計算機ENIACは1.8万本の真空管と6千個のスイッチを用いた巨大な装置で運用にも苦労があったが、トランジスタの登場により小型化と高速化が一気に進んだ。1997年、IBMのディープブルーがチェスの王者カスパロフに勝利し、2016年にはグーグルのアルファ碁が囲碁棋士イ・セドルに勝った▼
近年では、くら寿司のAIロボットが1時間に3600貫を握り、コジマ技研工業の串打ちロボットは1時間に1500本の焼き鳥を処理するなど現場への導入も進んでいる。また、ChatGPTなどの対話AIが一般にも普及し、グーグルやマイクロソフト、アップルもAIアシスタントの機能を提供している▼
一方、課題も多い。AIがつくった女性に心を寄せた男性が自殺する事件や、権力者によるAIの恣意(しい)的な操作、さらにAIが暴走し人類が支配されるといったSF的なシナリオも議論されている▼
「AIを制する者が未来を制す」ともいわれる時代、日本はAI人材の層が薄いとされている。今後は文理融合を進め、小中高や高等教育でAI教育を積極的に展開し、実社会で活用できる力を育てることが重要である
(政治経済社会研究所代表・中山文麿)