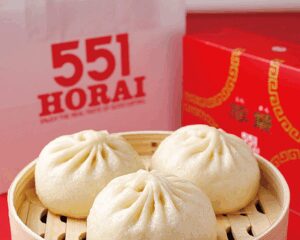「お客さまにも、仕入れ先にも、そして一緒に働いてくれる仲間にも、本当に人に恵まれてきました」
そう語るのは、北海道旭川市で自転車とストーブの専門店「高砂輪業」を営む代表取締役・左高芳則さんである。1972年の創業から半世紀、人口減少や物価高騰、競争激化という逆風を跳ね返し、売り上げを15年で約3倍に伸ばしてきた。
初代・好信が始めた自転車修理業は、夏は自転車、冬はストーブを扱う「季節連動型」の形に発展し、地域の暮らしに欠かせない存在へと成長した。しかし、経営の柱だった大口取引が突然打ち切られ、売り上げは3割以上減少。まさに存続の危機に直面する。
危機を越え地域密着へ注力
そこで2代目の芳則さんは大きな決断を下した。「ここからが自分の商売だ」と腹をくくり、経営の軸を地域密着へと転換したのである。新聞折り込み広告に代わり地域情報誌へ、自ら撮影・編集したチラシやSNS発信へと取り組みを変化させ、個人客一人一人との距離を縮める努力を続けた。
その根底にあるのは「手間を惜しまない姿勢」である。店頭には常時300種類以上の自転車を並べ、年齢や体格、用途に合わせて最適な一台を提案する。
小さな子どもには軽量で安全な車体を試させ、高齢者には安定性の高いモデルを紹介する。市内・近郊への無料配達や他店購入車の修理、盗難補償制度なども整え、顧客が「買ってよかった」と実感できる仕組みを築いた。
繁忙期には1日50台以上の修理が持ち込まれるが、整備士は「自分の家族が乗るつもりで整備する」を合言葉に妥協を許さない。高齢の顧客には修理内容を紙に書いて渡すなど、小さな気配りも徹底する。こうした姿勢が「地域に根ざす店」としての信頼を支えているのだ。
買った後の信頼とそれを支える人材
「うちは買って終わりじゃありません。むしろそこからが本番なんです」と左高さんは語る。
特に冬場のストーブは生活インフラであり、販売後の対応こそが信頼を左右する。同店では貸し出し用ストーブを100台以上確保し、故障時には即日対応できる体制を整備している。定期的に分解整備を呼びかけるDMやクーポンも、「暮らしを気にかけています」というメッセージを込めている。
ある年配の顧客から夜間に「ストーブがつかない」との連絡を受け、左高さんがすぐに駆け付け応急処置を行ったこともあった。顧客は涙ながらに感謝を伝えた。こうした一つ一つの行動が「また頼みたい」という気持ちを生み、次の利用につながっている。
さらに、同店の強みは「人」にもある。現在の社員は社長を含め12人で、20代から70代まで幅広い世代が在籍する。自動車整備士や歯科技工士、自衛官OBといった多彩な経歴を持つ人材が活躍している。長男の翔太さんも16年間勤務し、SNS発信や若年層への対応を担いながら次世代へのバトンを引き継いでいる。
社内の雰囲気づくりも大切にしている。ボウリング大会や打ち上げで交流を深め、休憩時間の雑談も欠かさない。「職場が楽しくなければ、お客さまにも伝わる」と左高さんは語る。かつて83歳まで現場に立ち続けた社員がいたほど定着率は高く、安定したサービス提供の土台となっている。
今後は自転車やストーブに加え、リフォームやエアコンの販売・施工にも注力する計画である。いずれも暮らしを支える基盤であり、提供する価値は「安心と信頼」である。
「これからは〝誰から買うか〟がますます問われる時代です。だからこそ〝またあの人から買いたい〟と思ってもらえるように、心を込めて仕事をしたい」 その言葉には、商人としての誇りと未来への覚悟が込められている。地域の暮らしを支える高砂輪業の挑戦は、これからも続いていく。
(商い未来研究所・笹井清範)