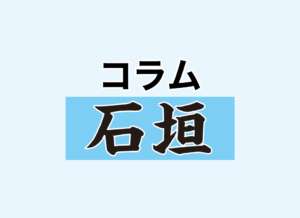トランプ政権の高関税政策は、世界を「理想」と「現実」の板挟みにし、各国に厳しい選択を迫るものとなった。米国から突き付けられた難題を乗り越えるため、多くの国は、今日まで掲げてきた自由貿易という理想を手放し、米国との交渉に応じた。日本もまた、対抗措置は取らずに米国との合意を優先した。戦後の理念に逆行する動きにもかかわらず、市場経済は急速に悪化することなく持ちこたえ、まるで各国の現実路線の対応を評価しているように見える▼
私たちの前には二つの道がある。一つは、このまま米国の政策に従う道である。この場合、日本は米国の影響を強く受け、政府による国内産業保護に比重を置く政策に傾くことになるだろう。もう一つは、「自由と平等」という価値を土台に、国際社会の秩序を立て直す道である。米国の政治経済学者バリー・アイケングリーンは、日本経済新聞の「経済教室」で、米国が必ずしも頼れる同盟国ではないことを前提に、アジア地域が欧州のように独自に安全保障や経済の強化に取り組めるかどうかと投げかけている▼
米国と同盟を結ぶ日本にとって、この立て直しの道は困難であり、彼の提案は理想論に聞こえるかもしれない。しかし、日本が戦後の繁栄を享受できたのは、国際社会にその秩序が存在したからだ。アジア地域の発展のために、日本が国際秩序づくりでリーダーシップを発揮する必要があることは明らかだ。日本には、目前の現実にリアリズムで対応しつつ、将来を見据えた理想の国際秩序を再構築するための主体的な選択と行動が求められる。アジアの自由主義国家として、この秩序を後世につなぐという責任を果たせるかが、今、問われているのだ
(NIRA総合研究開発機構理事・神田玲子)