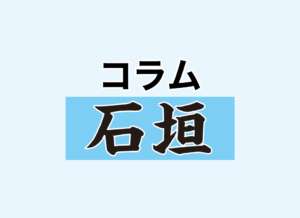日本遺産(Japan Heritage)の創設に関わって、はや10年目を迎えた。今や全国に104の優れた日本遺産の物語が認定されている。当初は世界遺産(World Heritage)の日本版といった言い方もあったが、この二つの制度はその発足の経緯も目的もまるで異なる▼
世界遺産は、1972年のユネスコ総会で採択された世界遺産条約(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約)に基づいて制定された。「顕著な普遍的価値」を持ち、人類共通の財産として過去から現在へと受け継がれ、未来へと伝えていくべきかけがえのない宝物の保全が目的である。日本は条約の批准が20年遅れたが、93年に最初の法隆寺地域の仏教建造物や姫路城などが登録され、現在26の文化遺産・自然遺産が登録されている。72年の世界遺産条約から53年、日本の批准からもすでに33年がたっている▼
言うまでもなく、世界遺産は、人類共通の遺産を損傷や破壊の脅威から国際的に保護・保全し、未来世代に引き継いでいくことを目的としている。これに対して、日本遺産は、地方自治体からの申請に基づき文化庁が認定する。貴重な歴史文化資源を次代に引き継ぐための保全措置は当然だが、指定文化財以外の多様な文化資源を点ではなく「面」で捉え、かつこれらストーリーによってパッケージ化して活用し、地域活性化を図ることを目的としている▼
日本遺産はその認知度が低い点が指摘される。世界遺産と比べると歴史が圧倒的に短いことから当然でもある。しかし、今や観光など地域活性化において「物語」手法は大きく定着した。物語化は地域の差別化・ブランド化でもある。次の10年にさらに期待したい
(観光未来プランナー・丁野朗)