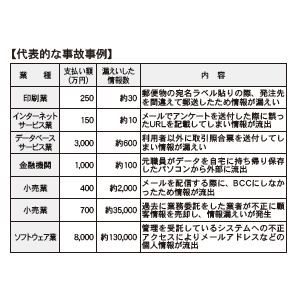補償の対象
補償の対象は、情報漏えいの結果、加入者(被保険者=保険契約により補償を受ける方)が被った経済的損害で、次に挙げるものとなる。
(1)賠償損害補償(情報漏えい賠償責任補償特約)
①基本リスク
被保険者(加入者およびその役員)自らの業務遂行の過程における情報の管理、または管理の委託に伴い発生した情報の漏えいに起因して、日本国内において保険期間中に発生した、被保険者が法律上の損害賠償責任負担を被る損害(損害賠償金、争訟費用など)に対して、保険金を支払う。
②求償リスク
被保険者が、他の事業者から受託した情報を漏えいさせ、その委託者から、日本国内において保険期間中に、損害賠償責任請求がなされたことにより被保険者が被る損害に対し、保険金を支払う。委託者からの損害賠償請求には、委託者が事故対応のための措置を日本国内で講じることによって被る費用損害を含む。
(2)費用損害(個人情報漏えい費用損害補償特約)
被保険者が、業務遂行過程における個人情報の管理または管理委託に伴い発生した個人情報の漏えいにより、被保険者が行った引受保険会社に通知した日の翌日から180日間で、必要かつ有益な措置によって被る費用損害に対して保険金が支払われる。
具体的には、謝罪広告掲載や謝罪記者会見、通信、お詫び状作成、コンサルティング、見舞金・見舞品購入、事故原因調査、コールセンターへの委託などに関わる費用のほか、職員の超過勤務手当、交通費、宿泊費、弁護士報酬などが含まれる。
制度の特長
(1)団体割引(20%)適用による割安な保険料
(2)情報管理体制・認証取得状況により最大60%割引
①「告知事項申告書」により情報管理体制が良好であれば最大40%割引
②プライバシーマーク、TRUSTe・BS7799/ISMSの認証取得で最大30%割引。①と合算して最大60%の割引を適用することが可能となる
(3)漏えいの時期を問わず補償
(4)幅広いリスクカバー
①クレジットカード番号、死者情報、従業員情報(ただし、見舞金・見舞品費用は対象外)、紙データの漏えいも対象
②一般に予防策を講じにくいとされている、使用人などの犯罪リスクによる損害も補償
(5)「個人情報漏えい時の対応ガイド」の提供
(6)「リスク診断サービス」(無料・任意)の提供
休業補償プラン 病気やケガで働けなくなることは事業存続のリスク
就業不能中の所得をしっかり補償
経営者の長期入院は、企業の存続に関わる大きな問題だ。さらに、金融機関から融資を受けていたり、住宅ローンがあったりする場合には、経済的に甚大なダメージを受ける。休業補償プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用することができる。
本プランは、商工会議所会員企業の経営者本人および従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーするもの。生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるようになっている。
収入喪失リスクのカバーは、日本ではこれから普及が期待される分野である。アメリカでは、19世紀後半に就業不能保険が登場して以来、目覚ましい発展を遂げ、今では1兆円を超える市場規模となっている。
日本での加入者は、医療業や情報サービス業、専門サービス業など、専門的な職業従事者と自営業が多いのが特徴だが、最近は事務職の加入が増加している。また、大企業では、社宅や保養所を廃止し、従業員が選択できる新しい福利厚生制度(カフェテリアプラン)が普及してきている。この動きは、中小企業にも広がりつつある。
本プランは、割安な保険料で加入でき、手続きも簡便である。特に公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者にとって、メリットが大きいといえるだろう。
休業補償プラン 加入者の体験談
経営断念の不安から救ってくれた保険です
設備工事業経営・Aさん(42歳)
兵庫県在住/休業補償プラン3週間
休業補償プランは、商工会議所の福利厚生制度として紹介されました。10年以上これといった大きな病気もありませんでしたが、私自身もそろそろ体力的に心配になってきたことから保険の加入を検討していました。そんなときに知った商工会議所の休業補償プランは、一般の保険に加入するよりもかなり割安だったこともあり、私より妻の方が積極的でした。妻にとっては、毎月の生活費が補償されるという点が魅力だったようです。
加入して3年目、私は出勤途中に突然意識を失い倒れました。原因は脳梗塞。幸い近くにいた人が救急車を呼んでくれて、すぐに病院に行くことができ、また症状も軽かったことで手にしびれが残る程度で済みましたが、自営業者は自分の体だけが頼り。そのため、収入が減ることにも大きな不安がありました。
しかし、商工会議所の保険に加入していたことを思い出し、その後は安心してリハビリに集中することができました。3週間後、仕事に復帰し、その後約35万円の保険金が支払われたので大変助かりました。
商工会議所の制度は本当に頼りになりました。
業務災害補償プラン 高まる企業の労災リスク
裁判で遺族側勝訴が相次ぐ
過労死を巡る裁判で、従来より企業や経営者の責任を明確にする判決が増加している。平成26年11月より過労死等防止対策推進法が施行されるなど、従業員の労務管理について、企業側の対応がこれまで以上に問われている。
業務災害補償プランは、従来型の負傷型労災といわれる業務中のケガ、および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば安全配慮義務違反を問われた)場合に発生する、企業の損害賠償責任(賠償金など)に対応する制度である。
労災発生時に求められる責任
労働災害が発生し、労働者が死傷すると、企業には一般に次のような法的責任が発生する。
①民事責任
使用者に安全配慮義務違反あるいは過失などがあれば、被災労働者またはその遺族から民事上の損害賠償を請求される。この場合、業務に起因する災害であれば、労災保険による労災が給付される。
②行政責任
労働基準監督署長から作業停止処分、建物などの使用停止処分などを受ける。建設業者の場合、業務停止処分や公共工事の指名停止処分などを受ける。
③刑事責任
業務上過失致死傷罪あるいは労働安全衛生法違反などの責任を問われる。
④社会的責任
マスコミによる報道などにより、取引停止など社会的信用を失う。
民事責任に対応
業務災害補償プランは、この4つの責任のうち、①民事責任すなわち、使用者責任を補償するものとなっている。
労働者が業務中に負傷するなどの労働災害が発生した場合、使用者(経営者)は、労働者またはその遺族から、民事上の損害賠償を請求される。損害賠償には、主に治療費(死亡・後遺障害の場合は逸失利益)や休業損害、慰謝料、弁護士費用などが含まれる。労働者が死亡した場合、企業の民事賠償責任が1億円を超えるような高額になるケースもあり、その額は年々上昇している。
一方、損害賠償金を支払えなければ、事業継続が不可能になることもあり、その場合、これまで雇用していた多くの労働者も路頭に迷うことになる。
本プランは、業務上の事故による死亡・後遺障害・入院・手術・通院はもちろん、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害をカバー。事業継続の大きな一助になるといえる。
また、前述のような新しい企業責任(安全配慮義務違反などによる企業の法律上の賠償責任)のほか、例えばうつ病などの精神障害による「過労自殺」「過労死」が原因で認定された労災など、法律上の企業責任(民事賠償金)を問われた場合の慰謝料や訴訟費用(弁護士費用など)も対象になる。
「心の病」対策の義務化
厚生労働省は、労働安全衛生法の一部を改正した。施行日は平成27年12月である。その中には、中小企業を含む全企業のメンタルヘルス対策の義務付けが盛り込まれている(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)。
全従業員に年1回、医師か保健師による「心の病」のチェックが必要になる。厚生労働省の試算では、面接を含めた一人あたりの検査費用は350円。対象者は3000万人程度と見られ、産業界全体で100億円を超える新たな負担が生じると試算されている。
メンタルヘルス対策は中小企業では普及が遅れているため、法律が施行されれば、大半の企業が対策を迫られそうだ。
加入しやすい保険料水準と手続き
本プランの保険料は、補償内容が同じ一般の保険に比べ半額程度に設定されており、業種を問わず多くの事業者が加入している。売上高を基に保険料を算出する仕組みであるため、加入に当たっては従業員数を保険会社に通知する手間がなく、パート・アルバイトが多い製造業・小売業には利便性が高い。また、役員を含め全従業員が自動的に補償対象となることから、中小・中堅や下請けを抱える事業者などに活用しやすい内容になっている。
最近は過労死に対する取締役個人の責任を認める判決も出た。従業員労務対策はこれまで安全配慮義務の実施、福利厚生といった観点で捉えられてきた。だが、今後は少子高齢化による労働人口の減少などに対応した人材確保の観点から考える必要があるだろう。従業員の心身の健康を保つことは、企業にとって効率的で持続的な成長への投資となるはずだ(図)。