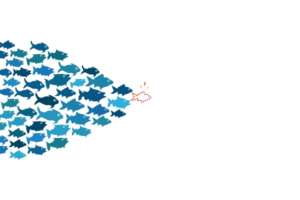金融専門家の間では、以前から「10年周期で世界の金融市場に大規模な金融危機がやってくる」という見方がある。具体的には、1987年以降、1997年、2007年と、末尾に7が付く年に金融危機が起きており、今後もそうしたサイクルで金融市場の混乱がやってくるかもしれないというのだ。
1987年には、ニューヨーク株式市場の暴落に端を発した、世界的な株価の急落(ブラック・マンデー)があった。ニューヨークの株式市場は、ドル金利引き上げの思惑などを背景に、前週末比20%を超える下げを演じた。その後、米国株式市場が本格的に立ち直るまでに多くの時間を要したことは、まだ記憶に新しい。 97年7月には、タイ・バーツの変動相場制移行に端を発し、アジア通貨危機が発生した。当時、東アジア諸国は高い経済成長を実現しており、それに呼応して、海外から多額の投資資金が流入していた。ところが、当該諸国の成長率が鈍化したことに伴い、投資資金が流出し始め、アジア諸国の通貨が一斉に売りを浴びて急落した。その結果、インドネシアや韓国などに通貨危機が波及し、外貨建て債務が膨張したことで、国内の金融システムが混乱した。最終的にはIMF(国際通貨基金)が救済する格好で事態は収束したものの、一時は世界経済に重大な悪影響が出ることも懸念された。
そして2007年には、米国の金融市場のサブプライム問題が顕在化した。2000年代前半から、米国では不動産価格の上昇が顕著になっており、不動産バブルに対して警鐘を鳴らす専門家もいたが、その後も価格はますます上昇。金融機関は不動産取得者の増加に対応して、住宅ローンの貸し出し基準を緩める方針を取った。
その結果、信用力の低い人々にも多額の住宅ローンが貸し出されることとなった。それまで上昇を続けていた住宅価格が06年の年央以降に下落傾向に転じると、返済能力が低い住宅ローンの焦げ付きが大量に発生。多くの米国金融機関は不良債権処理に追われ、経営状況が悪化した。さらに、住宅ローンを基にした証券化商品が、米国のみならず欧州などの投資家に広く拡散していたため、世界的な金融混乱を引き起こし、最終的にリーマンショックへと結び付くことになったのである。
こうして過去の歴史を振り返ると、確かに、10年周期で金融市場は危機的な状況に陥ってきた。このサイクルに従うと、「2017年にも何か起きる」と考えるのはそれなりに理解できる。そうした金融危機発生の背景には、米国の金融政策に緩和から引き締めへの転換があったことを忘れてはならない。金融政策が転換されることで、金融市場から投資資金が逃げ出したことが経済に重要なインパクトを与えたと考えられる。一般的に、自由主義経済には景気循環の波動が存在する。米国経済のケースでは、約10年の建設需要の波が景気の波を形成しているとの見方が有力だ。その意味では、10年周期の世界的な金融市場の変動サイクルには、それなりの説得力があった。そうした状況の下、景気の変動と金融市場のサイクルを結び付けるものが金融政策だ。それは、金融政策の変更が、金融市場に変調を与える要素になっているからだ。
FRB(米連邦準備制度理事会)は今年の初めから量的金融緩和策第3弾(QE3)を段階的に縮小して、14年10月までに終了することを決めている。この流れに従うと、15年中には政策金利が引き上げられることになると見られる。一連の流れは、明らかにFRBが金融政策を引き締め気味に変更することだ。
そうした措置によって、株式などの金融市場から一部の資金が流れ出すことは避けられないだろう。それによって、株式市場などが不安定な展開になることも考えられる。そうした引き締め効果が徐々に効果を発揮すると、株式市場が調整局面を迎えることは十分に想定される。そして、そうした調整幅が大きくなると、世界の金融市場にマイナスの影響を与えることになる。2017年金融危機説は、あながち荒唐無稽とは言えない。