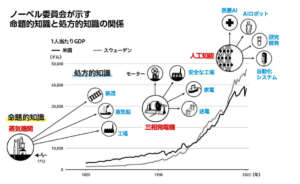「デミニミス・ルール」という舌をかみそうな用語が、メディアをにぎわしている。外国から輸入される個人向けの少額の小口貨物に適用される免税措置で、「デミニミス」は「ささいなもの」を意味するラテン語だ。小口貨物を全て開封して、内容と申告額が一致しているかを確認する手間を省略する狙いがある。この制度を主に中国発で米欧、日本などに輸出する越境ECのSHEINやTemuが利用したことで、世界的に小口貨物が急増し、課税逃れや違法な輸入品が黙認できないレベルに達したため、規制論が台頭した。加えてトランプ政権が中国からの輸入を抑制するため、4月にデミニミス・ルールを廃止したことで、EU、日本やベトナムなど東南アジア諸国でも見直しや利用の厳格化を進めている。
SHEINなど中国の越境ECは、生産地を広東省や浙江省に集中させ、在庫を1カ所に集め、世界に発送するというビジネスモデルで急成長した。国際航空貨物の料金はかかるが、米欧日などに中間在庫を置く物流拠点を持つよりも合理的という判断は鋭かった。昨年は米国に届く小口貨物の3分の1、EUでは40%が中国発の越境ECだったという。デミニミス・ルールの適用が除外または限定されれば、SHEINなどは事業の抜本的な見直しを求められる。
今、浮上しているのは大消費地で生産し、国内配送する手法だ。米国、EUなどで衣料品、日用品を生産するのは高コストだが、中国で原材料を裁断、着色、コンポーネント化など半加工してから消費地に送り、そこで縫製、組み立て、検査などを行い完成させ、国内配送する方式は中国発の越境方式に比べ、配送や在庫のコストを下げ、関税回避のメリットもあり、逆転の発想になる可能性がある。
ここで注目すべきは日本国内において多品種少量で、短期集中、短納期の衣料品、日用品を生産する需要が増える可能性だ。人手不足、人件費高騰の日本でそんなことできるはずがない、と言ってしまえばチャンスは去っていく。高齢者、外国人の雇用、隙間時間にバイトする若者の活用、非稼働時間の生産設備の利用など工夫の余地は大きいはずだ。筆者は過去25年間で延べ500カ所以上の国内工場を見てきたが、日本の中小企業の生産現場の創意工夫と柔軟性、変幻自在ぶりは世界トップと言っていい。過去20年間、中国に押され、その力を発揮する場がなかったが、トランプ関税により世界がモノづくりの見直しに向かう中で、日本にチャンスが来ている。