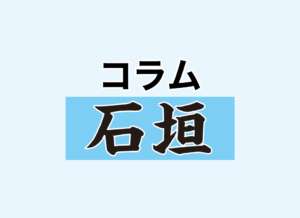世界のトップアスリートが参加する世界陸上競技選手権大会が9月に東京で開催される。驚異的な記録ラッシュや一流選手同士の争いが注目されよう。海外と日本の選手とでは体格以外にも大きな違いがある。海外は大半が個人で活動しているのに対して、日本の場合、働き方が多少異なっていても企業に所属しているケースが多い▼
1964年の東京五輪を契機に急速に拡大した日本の企業スポーツだが、バブル経済崩壊後、運動部の廃部や活動休止が相次いだ。業績が悪化する中で「福利厚生の一環」「企業イメージの向上」といった理由だけでは、株主に説明できないと判断したためとみられる。一方で廃部したチームを、選手を含め丸ごと引き受ける企業が相次ぐなど企業スポーツが衰退したとまではいえない。「企業のブランディングや従業員の求心力維持のために自社のチームが欲しい」(新興企業経営者)というトップは少なからず存在する。ただ、知名度のある選手を抱えるには相当額のコストがかかる。株式の配当や賃上げの原資に回さずに、チームの費用を負担してどの程度の効果があるか、数値で示すのは極めて困難だ▼
チームを持とうとする経営者は「企業のビジョンとの整合性を説明することが必要だ」と、複数の有力スポーツ団体で役員を務める須藤実和さんは指摘する。企業スポーツを投資と捉えれば「経営の軸」と合致する必要があるというのだ。「地域再生」「SDGs(持続可能な開発目標)重視」などの理念はスポーツ振興と共通点がある。「この考え方を進めるには自社でスポーツに取り組むことが効果的だ」と説明する根拠を持っていれば株主総会で責め立てられる恐れも少なくなろう
(時事総合研究所客員研究員・中村恒夫)