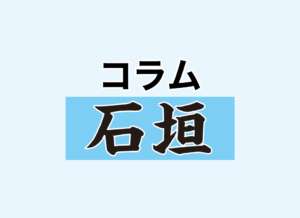この秋、自然科学分野で、2人の日本人研究者がノーベル賞を受賞した。日本の科学力が健在であることを示す出来事である。卓越した人材を育てるには、互いが刺激し合い、自由な発想を育む環境が必要だ。日本初のノーベル賞受賞者である湯川秀樹氏は、著書『創造的人間』で、当時の日本が欧米に比べ創造性を育む環境を重視していないことを憂い、創造力を発揮できる環境の重要性を説いた▼
人口減少と高齢化が進む日本にとって、イノベーションこそが成長の鍵となる。だが、創造力は、研究者に対する支援だけでは育たない。創造力は社会構造と密接に関連しており、特に、市場構造の在り方が創造性を左右する。日本では企業数が多過ぎて、過当競争に陥りやすいといわれる。赤字でも操業を続けてしまう結果、価格競争が激化し、利益率は下がる。こうした環境では、企業がじっくりと研究開発に取り組む余裕を持ちにくいと、一橋大学の吉岡徹准教授は指摘する。市場での過度の競争が、創造力の芽を摘んでいることになる▼
しかし、これを是正するのは困難だ。日本では戦後に築かれた「雇用を守る」文化が根強く、経営者の規範ともなっている。また、政治的にも赤字企業の支援が支持されやすい。結果として、創造性を生むための政策が展開しにくい状況が続くが、打開策はあるか▼
国が大胆な一歩を踏み出せないなら地域から変化を起こせばよい。地域が主体となって、創発が生まれる社会とそこで活躍する人材を育成していく。地域から新たな発想や挑戦が生まれれば、やがて国全体のイノベーションにつながっていくはずだ。創造力の芽を開花させるための豊かな土壌づくりが、地域に求められている
(NIRA総合研究開発機構理事・神田玲子)