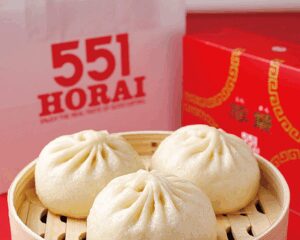朝7時、本店の扉が開くと、通りいっぱいに甘く穏やかなパンの香りが広がる。まだ通勤ラッシュ前のまちで、制服の高校生、出勤前の会社員、朝食を求める年配客が次々に列をつくる。
注文カウンターでは、白衣姿のスタッフがコッペパンを縦に切り、あんバター、ピーナツ、たまご、コンビーフと、注文に応じて具を次々に挟んでいく。これが、この店のいつもの朝だ。
岩手県盛岡市に本店を構える「福田パン」は平日で約1万個、休日には1万5000個を焼く。盛岡では「朝、福田パンを買う」ことが生活のリズムであり、まちの記憶の一部になっている。
創業の理念は「学生を満腹に」
同店の原点は、戦後間もない1948年に始まる。創業者の福田留吉は、当時としては珍しい酵母研究者だった。物資の乏しい時代に「学生たちに安く、そしてお腹いっぱい食べさせたい」と願い、その思いをパンづくりに託した。
こうした理念から誕生したコッペパンは、一般的なサイズの倍近く。ふわっと、しっとりした食感で、このパン1個と牛乳1本でご飯2膳分に匹敵する満足感を得られるという。これは単なる〝お得〟ではなく、「満腹こそ安心」という当時の時代感情を、製品設計に置き換えたものだった。 留吉は、花巻農学校で教壇に立っていた頃の宮沢賢治の教え子であり、賢治の「まごころのあるものづくり」の精神を実直に体現した人物だ。理念を数値化し、生地設計とサイズに落とし込むその姿勢が、今日まで変わらぬブランドの礎になっている。
福田パンのもう一つの核は、「目の前で具を挟んで渡す」販売スタイルにある。お客は黒板のおしながきから、甘い系・総菜系合わせて50種類以上の具材を選び、スタッフがその場でサンドする。ライブ感ある工程がただの購買を〝食の体験〟に変えている。
一方で、オペレーションには明快なルールがある。「組み合わせは2種類まで」「甘い系と総菜系は混在不可」。自由を制限することで迷いを減らし、品質と回転を両立させている。
価格設定も絶妙だ。本店のあんバターは159円(税込み)、他メニューも100円台から300円台。「日常に手が届くぜいたく」を実現する価格構成となっている。
さらに特筆すべきは製法の〝中種(なかだね)法〟だ。中種法とは、あらかじめ粉と水、酵母を混ぜて中種をつくり、時間をかけて熟成させてから本ごねする製法である。手間はかかるが酵母の発酵が安定し、しっとり柔らかい生地ができる。発酵の再現性が高く、気温や湿度の変化に左右されにくいため、品質の安定にも寄与する。福田パンではこの工程を独自にアレンジし、発酵温度と時間を日ごとに微調整している。
パンづくりは昼から夜にかけて進み、最も効率的に窯を回すタイミングを設計。長年にわたって変えない仕組みが味の一貫性と信頼を守ってきた。
思い出を仕組みに変える地域戦略
福田パンは本店だけに頼らず、県内の高校や大学の売店、地元スーパー、病院などへも商品を卸し、生活導線の中に接点をつくってきた。〝学生時代に食べた味〟が大人になっても記憶として残るそれが盛岡で〝ソウルフード〟と呼ばれる理由だ。
店の世界観も徹底している。校舎風の外観、黒板メニュー、どこか懐かしい内装。青春の記憶と日常の味を結び付ける演出が、「また行きたい」と思わせる力を持つ。加えて、地域イベントや学校行事への協賛も積極的に行い、単なる食品メーカーではなく〝まちと共に歩む存在〟としての信頼を築いている。こうして〝味〟を〝関係〟に昇華させる仕組みが、地元との信頼を支えているのだ。
近年は本店のほかに市内に3店舗、姉妹店を福岡県に展開し、オンライン販売でも全国にファンを広げている。それでも、あくまで地元にこだわる。
福田パンの物語が示すのは「理念→体験→仕組み→接点」という一貫設計の重要性だ。商いは思いつきではなく、理念を構造にすることから始まる。あなたの商いでも、「誰のために」「どう届けるか」をもう一度問い直してみよう。その答えを行動に変えたとき、地域に根付く新しい〝福田パン〟が生まれるはずだ。
(商い未来研究所・笹井清範)