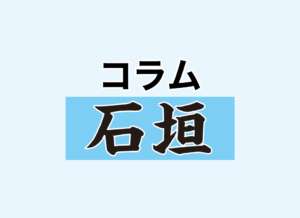デジタル化による技術の急速な変化は、市場での競争の概念を塗り替えつつある。ライバル企業との協力をあえて選択し、いち早く市場での優位な位置を確保しようとする企業が増えている。こうした企業戦略は「コーペティション」という。協調を意味するコーポレーションと、競争を意味するコンペティションを合わせてつくられた造語だ。
▼その代表例がアマゾンである。消費者はアマゾンのサイトを通して、アマゾン以外の小売店からも直接、商品を購入することができる。このマーケットプレイスという仕組みで扱われている数は、アマゾンが直接販売する商品の30倍以上といわれる。アマゾンにしてみれば、品ぞろえが増えることでサイトの価値が上がり、小売店側はアマゾンの看板を利用し売り上げアップにもつながる。
▼こうした両者の間には、本来の競合関係が生きており、どちらかが利益を失うリスクも高い。プラットフォーム企業が独占的な地位を乱用して不公平な取引を行っているという批判はよく聞かれる。政府が取る政策スタンスによっても両者の力関係は影響を受ける。
▼もう一つの事例は、台湾やイスラエル政府による国内の民間企業の対外連携への政策的な介入である。両国は、未熟な国内企業をてこ入れし、海外のグローバル企業との連携を促すことで、IT国家に脱皮することに成功した。政府の介入がなければ、周回遅れの国内企業を育成することもできなかったはずだ。
▼市場取引の公平性の判断や、内外企業の連携を後押しするための介入など、政府によって民間企業の競争力が左右される。コーペティション戦略に合わせた政策のアップデートを行う必要がある。
(神田玲子・NIRA総合研究開発機構理事)