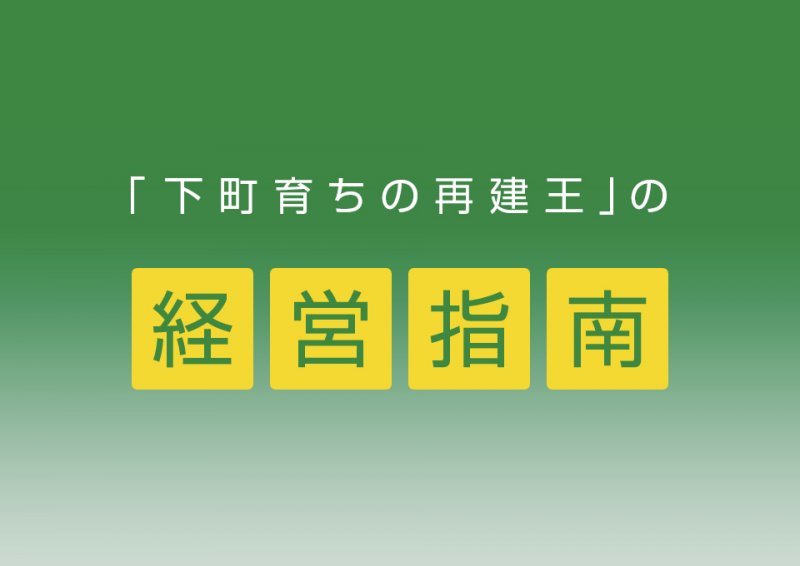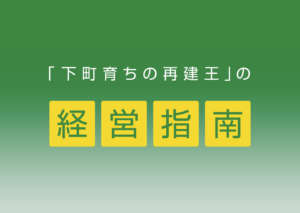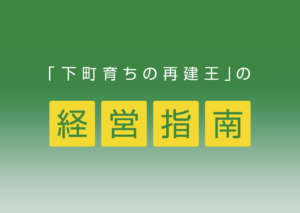「あなたは、仕事を抱えて、抱えて、抱えきれないものを部下に振っていますか? それとも、部下に仕事を振って、振って、振りまくって、部下ができないことだけを処理していますか? あなたはリーダーとしてどちらのタイプでしょうか?」
こう質問したとき、ほとんどの方がどちらであるべきかをわかっていながら、「前者である」と回答します。部下に仕事を振って、部下ができないことだけを処理するのが上司の仕事です。ところが部下のレベルが低いと、簡単なことだけを任せて、あとは全部上司が抱え込むしかなくなります。これは組織のレベルが低いということに他ならず、トップはそのことを認識しないといけません。
時々「私がやらないとダメなんですよ」と、何でもやる社長に出会いますが、その社長は人材をちゃんと育てられない人なのではないのでしょうか。
基本的に、仕事は社員がやるのですが、社員のできない仕事だけは社長がやる。社長は例外の仕事だけを担当する。(船井総研の創業者である)故・舩井幸雄氏はこのことを「例外の法則」と呼んでいました。
私事を例にとりますと、実家のディスカウントストアに25歳で入り、30歳で新店の店長になったときには、毎日12時間以上店で働いていました。そして毎朝、やることを重要な順にリストアップし、時間があればこれもやりたい、と理想的なことを書き並べるのですが、理想と現実は全く違います。面倒な電話がかかってくる、問屋さんが来る、アポなしの知人が来る、などといったありさまで、昼飯は3時過ぎまで食べられない。夜9時過ぎにやっと落ち着いて、「今日も忙しかったなぁ~」と一日が終わってみると、リストにあげたものの何もできてない……。そういう日々でした。店長でしたが、まるで雑用係でした。自転車置き場の整理から、ゴミ処理、スタッフが休む土・日には私がゴミ当番でした。組織が未熟だったというか、私が未熟だったのです。
それを実感したのは、6年ほどして次の店を出すことになったときでした。組織の権限を委譲してみると、担当者はきっちり仕事をこなしていったのです。もちろんスタッフの成長もあるでしょう。でも、仮にもっと早い時期であっても、任せさえすればできたのだと思います。その逆に、もし新店を出す計画が無ければ、私はその後も忙しい、忙しいと言いながら、仕事を抱え込んでいたかもしれません。
「例外の法則」を実践することは簡単ではありませんが、トップがそうすると決断する。そう決心することが最初の一歩。ここから本当の組織づくりが始まります。
お問い合せ先
社名:株式会社 風土
TEL:03-5423-2323
担当:髙橋