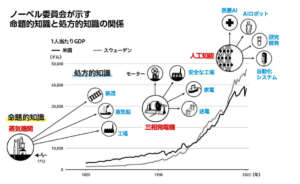深圳といえば1978年末に鄧小平氏が発動した「改革開放」政策の象徴として初の経済特区が置かれた街だ。外資を導入し、当時は賃金も安く、若くて豊富な労働力を活用して労働集約型の輸出型産業集積が構築された。その後、中国全土に広がった成長モデルをまさしく先導した場所である。だが、この10年ほどは中国の労働集約型産業が競争力を失う中で、関心を集める機会もなくなった。
今、その深圳が再び世界から熱い視線を浴びている。今回は「ベンチャーとイノベーションの都」としてである。中国政府的な表現では「創業創新」、縮めて「双創(シュアン・チュアン)」と呼ばれている。深圳には今世紀初めからテレビや携帯電話の中国メーカーがあったが、外資からの移転や模倣の技術で、イノベーションと呼べるものではなかった。日本人の多くの印象はそのままだろう。
空港や鉄道、道路の管制システム、再生可能エネルギーと火力発電を組み合わせた電力系統の制御、テレビやネット配信の放送システム、大都市の監視、治安維持システム――。深圳にある華為技術(ファーウェイ)の人材開発センターに設置された技術ショールームを見て、その先進性に驚きを感じざるを得なかった。日本のエレクトロニクスメーカーがこれからの収益分野として力を入れる社会インフラの大半がそこにパリ、ロンドン、ドバイ、バンコクなどに導入済みの商品として展示されていたからだ。
薄形テレビ、スマホなどハードだけではなく、ソフトやシステムで中国企業が先進国企業に急激に迫っていることは明らかだ。それは華為技術だけでなく、SNSの「微信」を展開し株式時価総額アジアトップに立ったテンセント、ドローン世界最大手のDJI、東南アジアでシェアを急伸させるOPPO、VIVOなどのスマホメーカー、第5世代通信で世界をリードするZTEなど、深圳に本社を置く企業群のグローバル市場での存在感で十分理解できる。
鄧小平氏が深圳を改革開放のスタートに選んだのは市場経済の香港に近いというだけでなく、保守派の巣窟の北京から遠く、目に付きにくいという理由があった。同じ理由で今の深圳のイノベーション力と勃興する企業群に日本企業はあまり気付いていないようにみえる。それは日本にとって大きなリスクである一方、深圳の新たな企業群を顧客として取り込み、高度な部品、素材を供給できる日本の中小企業にはまたとないチャンスが開けつつある。