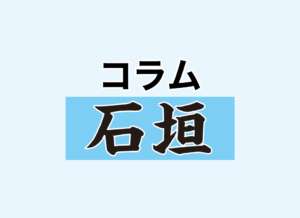タイムマシンに乗り込んで未来を確かめるわけにもいかず、一寸先に何が起こるかは誰にも分からない。それでも将来を予測する力が重要なことは疑う余地もない。現下を見れば、急速に進む円安。原因は、海外との金利差が拡大し、日本の資産保有の魅力が失われていることだ。先日、24年ぶりに、為替介入が実施された。しかし、話はそれだけで終わらない。急激な円安は何の予兆なのか。
▼もしかすると、政府や日銀の政策が手詰まりになる兆候ではないか。大量の借金を抱える日本政府、そして国債残高の半分を保有する日本銀行。両者の財務状況は、金利動向に大きく左右され、共に金利を引き上げることに慎重にならざるを得ない。それを市場は見透かしているのか。
▼あるいは、日本経済の中所得国化を見通している可能性もある。高齢化が進む中で、少子化の歯止めがかからない。労働制約が強まる中で、労働生産性の伸びの低迷も続く。数と質の面で課題を抱える日本が、経済大国としての地位を失うことを示唆しているのか。
▼最悪のシナリオは、日本の財政破綻である。インフレを抑制できなければ、日本の金利はじわじわと上昇する。国債の利子負担の増加に、日本の財政はどこまで耐えられるのか。最終的には行政サービスの提供も困難になるだろう。
▼これらの危機に陥らないための予防策は、データに見え隠れする悪い予兆を見逃さず、いち早く防御策を取ることだ。「想定外だった」というのは言い訳に過ぎない。タイムマシンがなくても、過去の教訓と蓄積されたデータを駆使して未来を予測することは十分に可能だ。悪い予感が的中する前に政府、日銀は議論を尽くし、対応する必要がある。 (NIRA総合研究開発機構理事・神田玲子)