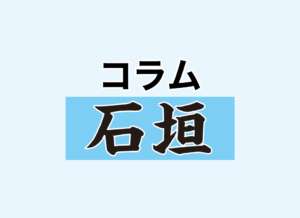政治・経済ともに先行き不透明感が深まった2024年。1月にトランプ氏が米大統領就任、4月には大阪・関西万博が開幕する25年はどのような年になるのか。本紙コラム「石垣」執筆者に今後の日本と世界の展望を聞いた。
分断を避け、平和の実現と経済拡大を
宇津井 輝史/コラムニスト
国民国家は17世紀の欧州三十年戦争後に萌芽し、18世紀のフランス革命後に世界に広まった。一つの国民が一つずつ国をつくる。まとまる仕組みとして合理的だから成功したが、それゆえに内向きになる。
一方、国家というのはある理念のもとに結成されたのだから、その正しい理念を広く世界に広める必要がある、と考える国がある。20世紀にコミンテルンを結成して全世界に社会主義を普及させる使命を負って建国したのがソ連である。だが理想とは裏腹に1世紀ももたずに崩壊した。
中国に中華人民共和国が成立したのは20世紀の半ばである。中華というのは世界の中心を意味する。世界は中国の言うことを聞くべきだと、自前の価値観の普及を「天命」とする国である。その表れの一つが一帯一路という統合の仕組みである。
18世紀に成立したアメリカ合衆国は、ヨーロッパの帝国から譲り受け、あるいは西部の開拓で広げた領土でいまの姿になった。その過程で身に付けた国家理念は自由と民主主義、そして開かれた市場である。これを世界に広める使命の前に国境はない。この3国の例は世界中をユナイテッド(統合)するのを最終目標とする、例外的な国家である。
アメリカがどんな大統領を選ぼうと自由である。だがアメリカが長く大切にし、それゆえに世界を牽引してきた理念は、国の成り立ちからもアメリカ人だけに共有されるものではない。アメリカが閉じてしまったら、はしごを外された世界が混乱するのは避けられない。
これをポピュリズムと片付けてはなるまい。不満と不安が広がる世界は二極が対立する「新冷戦」を内包している。
世界の国々はどちらかを選ぶ前に、平和の実現と経済の拡大を地球視点で求めるべき年である。
求められる「公正な社会」への脱皮
神田 玲子/NIRA総合研究開発機構 理事
今年の干支「巳(み)」である蛇は、成長の過程で何度も脱皮を繰り返す。もし、脱皮が不完全で古い皮膚が残ると、その部分では皮膚呼吸ができなくなり、命に関わるという。蛇にとって、新しい姿に生まれ変わることはリスクでもある。
社会も同様だ。古い制度や価値観から新しい仕組みに「脱皮する」ことは容易ではない。特に、公正な社会への変化は難題だ。戦後、先進国は個人の多様性を尊重し、少数派を包摂する社会を目指してきたが、それは、生活不安や所得格差への不満を持つ人々の反発を招いた。一部は移民排斥へ、また一部は政治エリート批判の形となって、昨今の政情不安につながっている。
成長を最優先に歩んできた日本は、「公正」の面で欧米や一部アジア諸国に後れを取っている。正規・非正規雇用の格差、フリーランスの雇用不安、配偶者控除制度の問題、同性婚の法的承認や外国人労働者の受け入れなど課題は多い。公正な社会への変化が難しい理由の一つは、何を「公正」とするかが、立場によって異なることだ。また、論理的には理解できても、感情的な違和感を覚える場合もある。さらに、公正性を強調し過ぎると、逆に「自分たちの権利が脅かされる」と感じ、政府に対して反感を抱く人々も増えよう。
それでも、私たちは、一人一人の生きがいや価値を等しく認めるという公正な社会の構築に取り組まねばならない。それを成功させるには、少数派と多数派の利害のバランスを図り、両者にとってプラスとなる方法を選択することが重要だ。また、双方の納得を促すためには時間をかける必要もあろう。公正な社会への変化は、古い価値観を脱ぎ捨てて新たな仕組みに変わる「社会の脱皮」、再生であり、私たちには成し遂げる覚悟が求められる。
すでに起きた未来
丁野 朗/観光未来プランナー・文化庁日本遺産審査評価委員
故木村尚三郎先生(東京大学)のご著書『ふりかえれば、未来』は、「自らの未来を拓くヒントは、その歴史の中にある」という示唆に富んだタイトルである。地域文化の普遍性とともに、その固有の歴史を見失うと、自分たちの独自性やアイデンティティーを見失ってしまうという意味でもある。
ここ10年近く文化庁日本遺産の事業に関わってきた筆者は、この言葉の重みを改めてかみしめている。社会が成熟し、ダイナミックな成長が止まった社会では、目先の違いに目を奪われ未来への志向性が弱くなる。同時に、自らが歩んできた歴史を見失ってしまう。いまの日本もまさにそのような状況なのだろう。
そんな中、年末に北海道の日本遺産ストーリー「炭鉄港」のシンポジウムに参加した。
舞台となった北海道は、明治から昭和の高度成長期までの100年間に人口が100倍にもなる急成長を遂げた。この成長の中核となった産業こそが石炭というエネルギー産業であった。空知の「炭鉱」、室蘭の「鉄鋼」、小樽の「港湾」、それらをつなぐ「鉄道」を舞台に繰り広げられた歴史が、「北の産業革命」という日本遺産物語となった。
その事業を当初からリードした友人の故吉岡宏高さんは、この物語のモチーフを「すでに起きた未来」と語っていた。
石炭と鉄鋼を軸に、現在の北海道の骨格を築いた絶頂期から1960年代以降の凋落(ちょうらく)の歴史は、日本がこれから経験する歴史を先取りする大きなヒントに満ちているという趣旨である。
薩摩の島津斉彬公が築いた幕末の集成館事業は、多くの薩摩藩士らと共に北海道開拓や今日の日本の礎を築いた。これからの100年、日本がどのような道をたどるのか。
「すでに起きた未来」を私たちは肝に銘じたい。
カスハラ対策で人材確保
中村 恒夫/時事総合研究所 客員研究員
東京都のカスタマー・ハラスメント防止条例が4月1日に施行される。「2025年はカスハラ対策が重要テーマになる」と大手法律事務所で労働問題を専門に扱う弁護士は予測する。きちんと対応できない企業は「人材不足で生き残りが厳しくなる」というのだ。
厚生労働省が実施したハラスメントに関するアンケート調査では、セクハラ、パワハラに次いで相談件数が多いのがカスハラだ。代表的なものは「長時間にわたるクレーム」「ひどい暴言」「土下座の強要など不当な要求」が挙げられる。特に、顧客ファーストを重視するサービス業では「自分は客だ」と居直り、担当者を責め立てる例が目立つ。
法的に見れば、事業者が従業員をカスハラから守る対策を怠ると、従業員への安全配慮義務違反により損害賠償責任を負いかねない。何よりも企業が毅然(きぜん)とした対応をしなければ、優秀な人材を確保することは困難だろう。教員のなり手が不足しているのは長時間労働だけでなく、クレーマーに近い保護者が少なくないからだ。もともと、常軌を逸したカスハラは刑法上の脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪などに問われる可能性がある。たとえ顧客でも違法行為には正当に立ち向かうことが社会的責任を課された企業の義務であるはずだ。ハラスメントを受けて傷ついた従業員へのケアも欠かせない。
「上得意客からの要望には応じざるを得ない場合がある」という意見もあろう。新条例は顧客に「条例ができたので対応しないと具合が悪い」と伝えておくきっかけになるのではないか。国も対策を講じるよう企業に義務付ける方向だ。「働きやすさは優秀な人材定着の第一歩」と先の弁護士は指摘している。
みんなに野球の楽しさと感動を与えてくれる、大谷翔平!
中山 文麿/政治経済社会研究所 代表
昨年は、毎朝、起きると、テレビで大谷翔平選手の活躍を見るのが楽しみだった。彼が加入したドジャースには、ポストシーズンで初回に3点以上取られた試合では「0勝14敗」と勝てないジンクスがあった。しかし、大谷選手はドジャースに加入した1年目でそのジンクスを打ち破った。彼は自らのバットで3ランホームランを放ち、チームの勝利に貢献した。
昨年の大谷選手の成績は驚異的で、ホームラン54本、打点130点、そして盗塁59を記録した。史上初となる「50本塁打・50盗塁」(50―50)を達成したのである。これがいかに偉業であるかは、「40―40」でさえ、史上6人しか達成していないことからも明らかだ。この記録を達成した大谷選手は、まさに歴史を塗り替えたといえる。 また、大谷選手は「スポーツ界のアカデミー賞」とも呼ばれるESPY賞を受賞したほか、傑出した打者をファンが選ぶハンク・アーロン賞や、最高の強打者に贈られるシルバースラッガー賞も受賞した。数々の栄誉は、彼の実力と努力の結晶だ。
技術面でも彼は進化を続けている。けがでバットを握れない時でさえ、練習場でバッターボックスに立ち、選球眼を養うトレーニングを欠かさなかった。また、野球一色の生活を送り、体調管理にも細心の注意を払っている。彼は「調子が悪いときこそ、技術的な向上のヒントが隠されている」と捉え、その状況をむしろ幸せと感じて研究を重ねている。
そして、今年のドジャースは3月18日と19日に東京ドームでカブスと開幕シリーズを戦う予定だ。この試合には、大谷選手をはじめ、山本由伸選手、カブスの今永昇太選手や鈴木誠也選手といった4人の日本人選手が登場する。今年も大谷選手の活躍が大いに期待される。