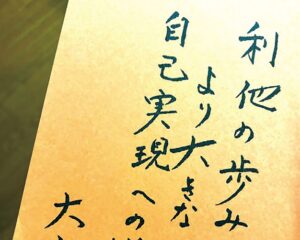写真館、アイスクリーム、日刊新聞、ガス灯など多くの日本発祥を持つまちがある。幕末にペリーが来航し、この地で日米和親条約が結ばれ、続く修好通商条約によって開港された5港の一つ、横浜。その表玄関、馬車道商店街である。当時、まちには外国人と舶来品が行き交い、多くの商人が集まった。
ところが、大火によってまちは焼き尽くされる。その後1867年、馬車が通れる道として整備されて以来、馬車道商店街は150年超の歴史と文化を持つ。関東大震災、横浜大空襲と2度にわたってまちが灰燼(かいじん)に帰すたびに、商人たちは自らの才覚と行動によりまちづくりに取り組んできた。
戦術よりも確固たる戦略
もっとも、こうした被害はこのまちだけの話ではない。日本各地に復興に努めた人がおり、まちはある。ただ、このまちにはまちを良くするもう一つの〝日本初〟がある。1975年に締結された全国初の地域主体のまちづくりルール「馬車道まちづくり協定書」である。
「まちづくりでは戦術はいくらでもありますが、しっかりした戦略を持つことが大切です。馬車道はまちづくり協定を戦略に据え、歴史と文化を生かしたまちづくりを進めてきました。これからも洗練された大人のまちを目指していきます」
こう語る馬車道商店街協同組合の六川勝仁理事長は、1946年に父によって創業された宝石商「アート宝飾」を営みつつ、父に続いて理事長を務め、まちづくりに取り組む。自らの事業でもギャラリーを運営するなど文化の醸成に努め、地域と社会に貢献してきた。
協定は冒頭で「〝日本の異国文化発祥の地〟として、開港横浜の歴史・文化を大切にするとともに、新しい文化を提案する」と基本理念をうたう。この理念の下、ハード面ではまち並み景観、建築用途、業種・業態の制限、建築物の高さ・デザイン、壁面後退、看板・広告物などを取り決め、ソフト面ではにぎわいづくり、商品開発、イベント参加、環境保全などを規定。根底には「人間優先のまち」という思想がある。
これまで数度の整備事業に取り組み得られた知見に合わせ、協定も2度の改定を行ってきた。その成果は、ぜひ訪れて確認してみてほしい。落ち着いた色合いで統一されたまち並み、街路樹を優しく照らすガス灯、広く歩きやすいレンガ舗装の歩道、随所にあるモニュメントとベンチ、元の外観を生かしてリニューアルされた歴史的建造物が日本有数の繁華街にあって他にない安らぎをつくり出している。
理想の未来像で賛同者を増やす
馬車道商店街のまちづくり協定書はその後、横浜各地のまちづくり協定書のモデルとなるとともに、全国のまちづくりにも大きな影響を与えていった。しかし、それらは当事者間の紳士協定であり、都市計画法や建築基準法のように法的拘束力を持たない。ゆえに〝絵に描いた餅〟となり、機能しない場合が各地で散見されるようになる。
馬車道商店街では、組合員自らが率先垂範しつつ、土地とビルを持つ大手企業に働きかけた。「まちづくりは最初から100%の人が賛成するわけではない。まちづくりが進むにつれて賛同者は増えていくが、こうした賛同者のためにもまちの将来を分かりやすく説明していくことが大切」と六川理事長は語る。
さらに、新たな開発に対してはまちと行政がスクラムを組んだ。事業者に対して横浜市が対応しづらいところは商店街が、商店街が対応しづらいところは市が対応した。欠かせないのは両者が協定書をバイブルとして守ろうという意思である。
「まちづくりには終わりはない。うれしいこと、悲しいこと、残念なことが毎日変化しています。ただ、今までの経験上、時間がかかることも、100%満足できないこともいろいろありますが、諦めては実現しません」
こう語る六川理事長が手にするのは、洗練された大人のまちの暮らしが描かれたイラストと文章。「馬車道スケッチ」と名付けられたまちの未来像である。こうした理想は協定書と共に、次代へと確実に引き継がれている。
(商い未来研究所・笹井清範)