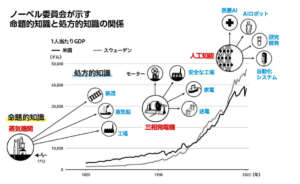「eスポーツ」という単語を見聞きする機会が急に増えてきた。eスポーツとは「エレクトロニック・スポーツ(electronic ・sports)」の略称。パソコン、スマートフォン(スマホ)などでプレーする電子ゲームを使ったスポーツ競技だ。スポーツといっても足や腕を使い、心拍が高まるような運動をするわけではなく、手先と動体視力、反射神経を駆使して戦う。サッカーやバスケットボール、バレーボールのように世界に広く普及し、米欧、中国で大規模な競技大会が開催されている。
ゲーム自身は個人や数人のチームで戦うが、それを数万人の観客が観戦。テレビやネットで中継され、プレーヤーに巨額の賞金が与えられ、さまざまな業種の企業が広告宣伝に活用する。ゲーム会社やゲーム機メーカーにとって、ゲームが注目されれば、売り上げ増につながる。サッカー、野球などのスポーツビジネスと同じ構造だ。
eスポーツでアジアは米国に比べ、市場の形成やプレーヤーの育成が遅れていたが、ここに来て、爆発的にeスポーツ市場が拡大している。考えれば、世界的にヒットするゲームは日本や中国発信のものが多く、ゲーム機も任天堂やソニーが世界に君臨している。若者のゲーム好きという点でもアジアは米欧に負けてはいない。今後、eスポーツはアジアで巨大ビジネスに成長するだろう。
すでに中国のアリババ、テンセントのIT2強はeスポーツに参入し、事業を拡大させているが、中国のeスポーツビジネスで最も著名なのは、万達(ワンダ)集団を率いる不動産王、王健林氏の息子の王思聡氏だ。彼が運営するチームは、世界的な強豪チームとしてのし上がっている。その姿は英国プレミアリーグのサッカーチームのオーナーと変わらない。 eスポーツは今年9月のアジア大会(ジャカルタ・パレンバン)でデモ競技に初めて採用され、2022年の中国・杭州のアジア大会で正式種目となる。2020年の東京オリンピックでも何らかの形で競技種目になる見通しだ。競技としてのeスポーツの発展とともにビジネスとしても急成長するだろう。
考えれば、eスポーツは男女も年齢も体格、体力も関係ない公平な競技であり、アジア市場こそメインの舞台となる可能性がある。旧来のスポーツの概念を崩すeスポーツのような新しい動きは、周辺に多様で幅広い新しいビジネスチャンスをもたらす。「自社とeスポーツの関わり」を、全社員を集めて議論してみてはいかがだろうか?