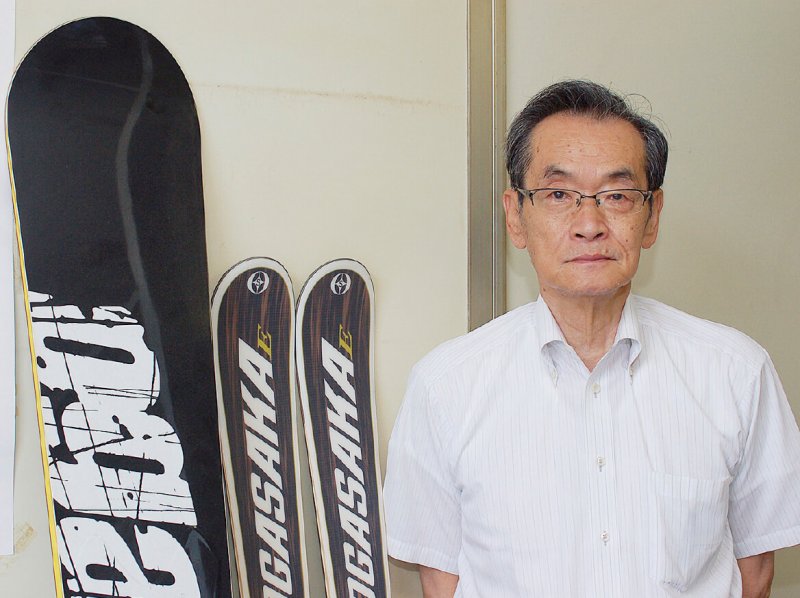一つの分野や自社の技術に徹底的にこだわり、業界No.1を維持し続けている、いわば「一点集中型」の企業がある。今号は、自社製品に絶対の自信を持ち、市場の変化にも負けない企業の視点と新たな戦略に迫った。
事例1 国内唯一のエッジメーカーとして決して「できない」とは言わない
打江製作所(新潟県上越市)
明治44(1911)年、日本に初めてスキーが伝来した新潟県上越市。いわばその聖地で打江製作所はスキーとスノーボードのエッジを製造している。従業員10人ながらも国内シェアは100%、海外でもエッジメーカーはほかにオーストリアとフランスに各1社あるだけだ。同社は、日本のスキー産業を支えている使命感から技術力アップに向けて常に努力を続けている。
農機具の部品からスキーのエッジ製造に転換
打江製作所が製造しているエッジとは、スキーやスノーボードの板の縁にある金属部品である。このエッジの性能によってターンの精度や滑るスピードが変わってくるため、製造には精密な作業が求められる。平成26年のソチ冬季オリンピックでは、国産のスキー板をはいた日本人選手がメダルを獲得している。この板にも打江製作所が製造したエッジが使われている。
打江製作所の創業は昭和35年、最初は地元の農機具メーカーの下請けとして部品を製造していた。そして40年ごろに農機具メーカーがスキーの板を生産することになり、その依頼でエッジをつくり始めた。現在、二代目社長として会社を経営している打江寿和さんは、当時をこう振り返る。
「同じ金属部品でも農機具部品とエッジとではつくり方が違う。そこで当時の社長だった私の父が、長野にあるエッジメーカーの工場へ見学に行きました。とはいえ、ライバルになるのですから、簡単に見せてくれるわけがありません。父は農機具メーカーの作業服を借りて、メーカーの人と一緒に工場に行きました。これからスキー板を生産する予定で、エッジを発注したいから見学させてくれと。悪い言葉でいえば技術を盗みに行ったのですが(笑)、父も職人でしたから、機械や作業を見て、こっそりとつくり方を勉強してきたわけです」
最初は農機具の部品と並行してエッジを製造していたが、50年代にはエッジに特化した。47年の札幌冬季オリンピックをきっかけに日本でスキーブームがさらに進み、スキー板の需要が急激に伸びたためだ。
「当時は30社ほどの国内メーカーが、合計で年間200万台ものスキー板を生産していました。エッジメーカーも約10社あったのですが、それでも生産が追いつかない。うちも従業員が30人ほどいましたが、それでも手いっぱいで、エッジに特化していかないと間に合わなくなったんです」
生き残っていくために新しい技術に挑戦していく
その後も、バブル景気や週休二日制の導入などによりスキー人口はさらに増え、各地にスキー場が新設されるなど、スキー産業は活況を呈していた。しかし、バブル崩壊とともにブームは下火になり、スキー人口は減少した。それとともにスキー板の生産量も激減し、国内メーカーも倒産や撤退が相次いだ。
「エッジメーカーも同様に減っていきました。でも、うちはもうエッジに特化していたから、やめるにやめられない。気がついたら国内でエッジメーカーはうちだけになっていました。このままでは国内のスキー産業は終わってしまう。頭を悩ませていると、スキーメーカーから、スノーボードをつくるから、そのエッジをつくってほしいというお話をいただきました。スノーボードのエッジをつくったことはありませんでしたが、もうそのときは、できるかできないかではない。スキーメーカーとともに生き残っていくためには、とにかくやるしかありませんでした」
エッジの製造では金型が重要になる。スキーやスノーボードの板は直線ではなく緩やかにカーブしており、特に先の部分はカーブの角度が微妙に変化しているため、それぞれのカーブに一つの金型が必要になる。先端部分だけで3つ、さらにそれを上に反らせるための金型も使われる。一つの板に8つの金型が必要になることもあるという。打江製作所でエッジの製造を始めて以来、ずっとこの金型をつくっているのが、現在は工場長を務める池内一郎さんである。機械でも難しい1ミリ以下の調整を手作業で行っている。その池内さんが中心となり、スキーとは形状が大きく異なるスノーボードという新たな分野に挑戦した。
顧客の要望に応えることで技術力を上げていく
スキーブームが終わると、若者の間でスノーボードが人気となっていた。するとスノーボードの板の需要も増え、すぐにスキー板の生産量を上回るようになった。国内唯一のエッジメーカーである同社も、これによりなんとか生き残っていくことができたが、大きな問題があった。
「スノーボードは小さいメーカーがいくつもあり、それぞれ形状が違って生産ロットも少ない。それに、最初はデザインも単純でしたが、今は差別化のために形状が複雑になってきていて、一つの製品に金型をいくつもつくらないといけなくなっています。一つの製品あたり何十台しか出ないんだけど、それでも金型をつくらなければいけない。決して楽ではありません。それに現在はスノーボードの生産量も、ピーク時に比べたら10分の1です。当社ではスキーとスノーボードを合わせて年間50万台のエッジを生産していますが、スキーの方が底を打って、最近は少し伸びているほどです」
そのため、「国内シェア100%といっても左うちわでやっていられるわけではない」と、打江さんは言う。国内にライバルはなく、切磋琢磨(せっさたくま)しあう競争相手もいないなか、どのような意識で技術力をアップしているのだろうか。
「お客さまからの要望です。お客さまからこういうのをつくってくれと言われれば、それが技術的に難しいものであっても、つくるしかない。スノーボードの角は円形が普通ですが、なかには多角形にしてほしいなどという希望もある。そういった声に試行錯誤しながらもなんとか対応していくことで、技術力をアップしてきました。うちがやらなかったらお客さまが困ってしまいますから」
同社には一つの信念がある。それは決して「できない」と言わないこと。国内唯一のエッジメーカーであるからこそ、できないとは言わないのだという。
スノーボード用のエッジの製造を始めてから、その素材となる金属の改良にも取り組み、メーカーと協力して、硬くて摩耗しにくい素材を開発した。硬い素材は加工が難しくなるが、それをうまく加工する技術も磨いていった。そうした努力もあって、今では海外メーカーにもエッジを供給するようになっている。
「ある海外のスノーボードのメーカーでは、製品カタログにエッジは打江製作所製と書いているところもあるほどです。日本製部品を使っていること、打江製のエッジを使っていることが、一つの売りになっているんです」
後継者を育成しエッジ一筋を強化
そんな同社が現在抱えているのが、後継者問題だという。
「うちの従業員はみんな20年以上のベテランで技術力が高く、それが強みなのですが、世代交代が難しい。今、若い従業員に技術の伝承を行っているところですが、うまくいくかまだ分かりません。また、私は二代目ですが、娘一人だけなので会社の後継ぎがいない。それが一番頭を悩ませている問題です」
この解決策はまだ見付かっていないが、これからもエッジをつくり続けていくことが、国内唯一のメーカーとしての使命だと考えているという。
「実は10数年前まで自動車のエンジンやゴルフクラブの部品も並行して製造していたことがありましたが、今はもう完全にエッジに特化しています。経営安定のためには三本柱を持った方がいいなどとよく言いますが、エッジづくりはあちこち手を出してやっていけるような甘いものではない。生産拡大ではなく技術力のアップを目指す。日本にスキー産業がある限り、これからもエッジだけをつくり続けていきます」
一つの製品に特化しているからこそつくれるものがある。打江製作所は世界でも3社しかないエッジメーカーの一つとして、一点集中にこだわっていく。
会社データ
社名:株式会社打江製作所
所在地:新潟県上越市字長面136
電話:025-523-3400
代表者:打江寿和 取締役社長
従業員:10人
※月刊石垣2016年10月号に掲載された記事です。