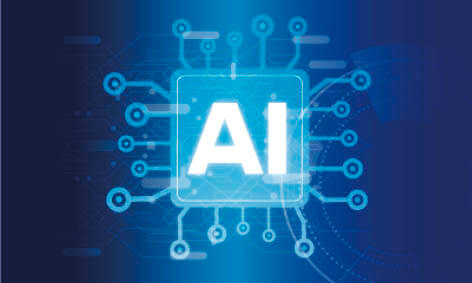最近、かつて半導体産業の盟主であった、米インテルの業況が芳しくないようだ。背景に、世界の半導体産業を取り巻く環境の変化がある。スマホの世界的なヒットなどを契機に、パソコンが中心だった需要は大きく変化した。さらに近年、スマホからAIへと変遷している。
それに伴い、有力半導体企業は、企画・設計から生産・販売まで全て自前で行う「垂直統合型」のビジネスモデルを変化させた。具体的には、各企業が自社の最も高い優位性を生かし分業体制で事業を進める「水平分業型」に変えている。それぞれの企業が相対的に狭い分野に特化し、ネットワークをつなぐ分業体制には、環境変化に対応しやすいメリットがある。現在では、先進半導体の生産を大手から引き受ける受託制度が、世界の半導体業界の中で主流を占めつつある。
以前の主力商品であったスマホでは、米アップルがわが国の電子部品メーカーから基板などを調達し、台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業傘下の中国企業・フォックスコンなどに製造を委託した。また、アップルは自前で製品の性能に適したチップを設計・開発し、TSMCに製造を委託。それが、世界的な水平分業体制への一つのきっかけになった。TSMCは、わが国の企業が製造するシリコンウエハーなどを調達することで、エヌビディアが設計開発を行ったGPUなどの良品率の向上を実現した。
TSMCは受託製造業に徹する、その製造ラインを活用し米GAFAMなどは自前で開発したAIチップを手に入れ、AIなどのトレーニングを増やす、という好循環が出現した。英アームの設計図を使って、AIに対応したパソコン向けの半導体を開発するIT先端企業も多い。それを好機に、わが国の企業は国際的な水平分業体制に寄与することができるはずである。わが国企業の高い製造技術にアクセスするため、対日直接投資を積み増すIT先端企業は増加傾向だ。
インテルの経営を担ったゲルシンガー氏は、最近、ビジネスモデルをうまく転換できず改革半ばで解任された。同社がたどってきた歴史は、おそらく多くの企業にとって重要な参考になるだろう。日米半導体協定などにより、1990年代以降、垂直統合型の事業運営体制を重視したわが国総合電機メーカーは、半導体市場で競争力を失った。しかし、半導体の製造には、素材や製造装置、超純水など多種多様な製造技術が欠かせない。その分野で、わが国には国際的な競争力を持つ企業が残っている。そうした重要素材や部材の供給能力があるため、TSMCだけでなく米マイクロンテクノロジー、韓国のSKハイニックスなどの大手半導体メーカーが、わが国での生産能力増強を重視している。
その意味では、国際的な水平分業体制は、わが国の企業が精密な製造技術を生かし、持続的な成長を目指す重要な機会になるはずだ。半導体部材などを扱う企業は、世界のIT関連分野の変化を常に注視し、ハードだけではなくソフトウエア開発のスピード向上に目を向けることが必要である。そして、そうした変化の中で、わが国企業はビジネスチャンスを的確につかむことが重要だ。
わが国の半導体政策にも変化が鮮明化している。政府は2024年度補正予算で、ラピダスへの支援を拡充する方針だ。戦略物資である半導体の製造能力は、国の経済の実力に直結する。それを民間企業だけのリスクテイク能力のみに委ねず、国がその一部をサポートすることは必要になるかもしれない。そうした傾向は、世界的にも見られるようになっている。大規模な半導体プロジェクトであるラピダスが、内外の企業と連携し先端チップの生産能力を発揮することができると、その影響はかなり大きくなるはずだ。その上で、海外のAIスタートアップ企業や、IT先端企業が開発したチップの受託製造が軌道に乗れば、関連産業の裾野は広がることが期待できる。インテルが乗り遅れた水平分業の波は、わが国半導体産業再興の重要な機会になり得るだろう。(2024年12月13日執筆)