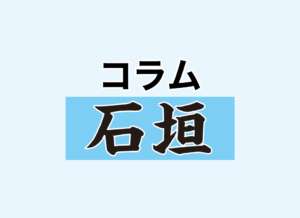産業が観光になる。いわゆる「産業観光」は1990年代半ば、「愛・地球博」の誘致が決まった愛知県名古屋市周辺で始まった。提唱者は当時、JR東海の会長であった須田寬さんである▼
2005年開催の愛・地球博に世界中から多くの観光客を迎えるのに、この地域は目ぼしい観光資源に乏しかった。だがトヨタ自動車をはじめ日本を代表するものづくり工場やミュージアムが集積するこの地の産業資源に着目した。産業系ミュージアム19館と連携し、これらの資源を丹念に調査した。鉄道やバスルート、見学時間などを調べ、手書きの見学推奨ルートも自ら編集した▼
こうしてスタートした名古屋の産業観光をモデルに、01年に「全国産業観光サミット」を開催、全国から集まる関係者に産業観光への取り組みを提案した。サミットでは産業観光を「歴史的・文化的価値のある産業文化財(機械器具・工場遺構など)、生産現場(工場・工房など)および製品などを観光資源とし、それらを通じてものづくりの心に触れる観光」と定義した。▼
以来、毎年各地で産業観光フォーラムやワークショップ、産業観光を通じたまちづくり大賞などの活動が続けられた。これらの活動は当時、須田さんが委員長を務めた日本商工会議所観光専門委員会(現観光・インバウンド専門委員会)や、会長を務めた「全国産業観光推進協議会」が中核となった▼
どんな地域でも産業(生業)のないまちはない。それは地域の個性でもある。ものづくりは地域の経済・文化の源泉であり、これらを基礎とした固有の観光ができる▼
須田さんは昨年12月13日、93歳で永眠されたが、この精神と活動は今後も長く継承していきたい
(観光未来プランナー・日本観光振興協会総合研究所顧問・丁野朗)