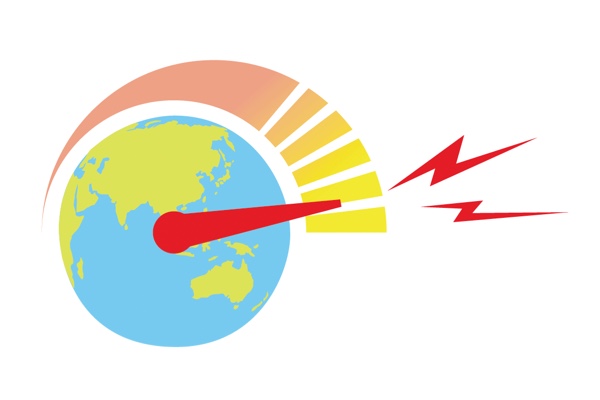2008年のリーマンショック以降、わが国や欧米諸国、さらには中国など多くの国々は景気回復を目指して積極的に金融緩和策を取ってきた。特に、わが国では日銀の黒田東彦総裁が異次元の金融緩和策と称して、思い切った量的・質的金融緩和策を実施した。そうした政策の効果もあり、株式などの金融市場は相応に安定した展開となり、世界経済は徐々にではあるが回復傾向が見られる。
しかし、その一方で、世界経済の回復ペースは期待したほど上がっていないのも事実だ。むしろ、足元では多くの国で、リーマンショック前と比較して成長率が鈍化している。それに伴い、消費者物価水準は低位状況が続き、企業間の取引価格を示す卸売物価指数は、マイナス圏に沈んでいる国や地域が多い。
13年3月、日銀が異次元の金融緩和策を実施する際、2年以内に消費者物価指数を2%まで引き上げると宣言した。岩田規久男副総裁は、「2%の物価上昇が実現できなければ辞任する」と言い切った。それにもかかわらず、日銀の宣言から2年半以上経過した現在、消費者物価指数の上昇は2%よりもはるかに低い水準にとどまっている。経済成長率も15年4-6月期にはマイナス1・2%に落ちこみ、景気回復のペースは緩やかだ。それは、わが国ばかりではなく積極的な金融緩和策を取ってきたユーロ圏諸国などでも見られる。そうした状況を冷静に見ると、現在、実施されている金融緩和策の効果には一定の限界があると見るべきだ。
金融緩和策は、基本的に金利の引き下げや、お金を供給することで企業や人々がお金を使いやすい状況をつくりあげ、経済全体の動きを活性化させることを主な目的にしている。しかし、中央銀行がいくらお金を印刷して市中に供給しても、企業や人々がそのお金を使わなければ、社会の中でお金はうまく回らない。
例えば、今、10万円持っていても、そのお金を使わなければ消費に結びつかないのだ。企業が多額の資金を持っていても、収益性の高い投資案件を見つけない限り、設備投資などにお金を使うことに結びつきにくい。中央銀行が積極的に量的金融緩和策を実施しても、その効果は、最終的に家計や企業の経済主体がどれだけお金を使う行動を取るかにかかっていることになる。消費者や企業経営者が先行きに不安を持つようなケースでは、期待されたほどの効果を発揮できない。その意味では、量的金融緩和策は万能ではない。
また、思い切った量的金融緩和策には、中長期的に弊害となる副作用も存在する。中央銀行によって供給された多額のお金によって、株式市場などでマネーゲームが横行し、理論的に正当化することができないほど株式などの資産価格が上昇してしまうことだ。80年台中盤以降、わが国が経験した〝バブル〟が形成されてしまうのである。中央銀行によって供給されたお金の一部は、もうかりそうな分野に投資資金となって流れ込む。「株を買えばもうかりそうだ」となると、多くの資金が株式市場に流れ込み株価を押し上げる。株価の上昇が企業業績の改善という経済の基礎的条件(ファンダメンタルズ)に相応する程度であれば問題はない。その場合、企業価値の増加に合わせて、株価は持続可能な安定した上昇が維持できるはずだ。
しかし、株価の上昇が続くと多くの投資資金が市場に流入し、ファンダメンタルズを無視した「買うから上がる。上がるから買う」という循環ができる。そうなると、株価の理論値(フェアバリュー)に関係なく、株価は上がり続け〝バブル〟ができ上がる。〝バブル〟は永久に続かない。〝バブル〟が崩壊すると、必ず景気は大きく落ち込み、それに伴い企業業績は下落する。企業の設備は過剰になり、設備投資のために多額の資金を借り入れていた企業などは返済ができなくなることもある。金融機関からの借り入れで投資を行っていた投資家も、返済が滞る可能性も高まる。不良債権が発生すれば金融機関の経営状況にも悪影響が及ぶ。政策当局は、金融緩和策の悪い副作用を十分に理解することが必要だ。