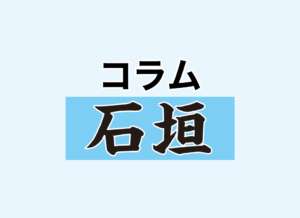9月1日は防災の日、台風シーズンの真っただ中だ。先の「令和2年7月豪雨」では、気象庁は熊本県人吉町周辺の24時間の降水量が200ミリメートルに達するとして周辺住民に厳重警戒を呼び掛けていた。ところが、驚いたことに2倍の400ミリメートル以上も降った。そのために、球磨川の水位は熊本球磨村渡の国土交通省の水位計で夜中の1時から5時間で8メートル近くも急上昇した。川が氾濫するのは当然で、多くの人が就寝中で逃げ遅れた。
▼最近、地球温暖化に伴い海水面温が1度上昇すると水蒸気量が7%上昇する。日本列島に大量の水分を含んだ大気の川が延びて線状降水帯の猛烈な雨を降らせる。このような暴力的な異常気象に対して、堤防をかさ上げしても無理だ。これからはハードに頼る防災から、自然と調和しながら洪水被害を減殺するソフトな防災に移行するべきだ。
▼例えば、日本には約1500の治水ダムと利水ダムが存在する。治水ダムを管理する国交省は利水ダムを管理する経産省や農水省と協議して豪雨が予想されたら1日から3日前にダムを事前放流して当該流域の河川の氾濫が避けられるようにした。
▼今や、日本のあらゆる河川で想定外の氾濫が起きても不思議でない状況だ。想像したくないが、荒川の決壊や氾濫、さらに台風に伴う高潮によって、江戸川区や北区の一部で最大10メートルまで浸水する危険性が叫ばれている。
▼われわれは当局が策定し始めた千年に一度起こるかもしれない洪水のハザードマップとにらめっこし、自分の行動手順を決めたマイタイムラインを策定して対処したい。政府の方でも、住民の避難のスイッチが入りやすいように勧告と指示の言い回しの改善など災害対策基本法を見直すようだ。
(政治経済社会研究所代表・中山文麿)