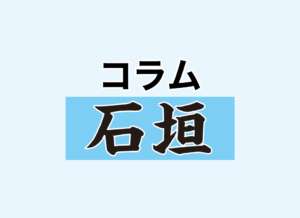話し言葉には流行がある。敬語が絡めば気になる表現もある。近ごろ耳につくのは「~してくださる」の多用である。当たり前の行為に対して「シェフが料理してくださった」「ゴミを回収してくださった」と言うのはいささか過剰表現である。見せかけの優しさを強調しすぎる世の風潮の現れであり、敬語表現の複雑な操作の罠にはまる一場面である▼
外部の人に対しては上司に肩書は不要と教えられた新入社員が、架かってきた電話を繋ぐ際に上司を呼び捨てにして周囲を凍らせるテレビCMも秀逸である。なんと面倒な世の中、と新入社員はため息をついたことだろう▼
4月は新社会人誕生の月である。仲間内で通用した話し言葉だけでは語彙の不足を痛感し、なおかつ日本語の敬語表現の難しさ、いやらしさを恨む季節でもあろう。筆者の自戒を込め、敬語を一人前に使いこなすにはいっとき「敬語の鬼」になる必要がある▼
日本語の敬語に、尊敬語、謙譲語、丁寧語の3種類があるのは誰もが知る。なぜそんなに複雑怪奇なのかと問えば、日本人が他人とのほどよい距離感や上下関係、敬意の度合いを話し言葉の中に込めているからである。相手をまつり上げ、自分をへりくだり、言葉がとがらないようにくるむ▼
敬語の達人であり、他人との距離の取り方の天才である京都人は、先生が「お言(い)やした」、配達員が「言うとった」、ご近所さんが「言うたはった」と使い分ける。これは京都の歴史が人々に厳しすぎたがゆえにたどり着いた処世術でもある。新社会人はみな希望をもって新しい門をくぐったことだろう。まずは真摯に仕事を覚え、周囲の人との距離感を学び、間違えながらも敬語を身に付けていってほしい。
(コラムニスト・宇津井輝史)