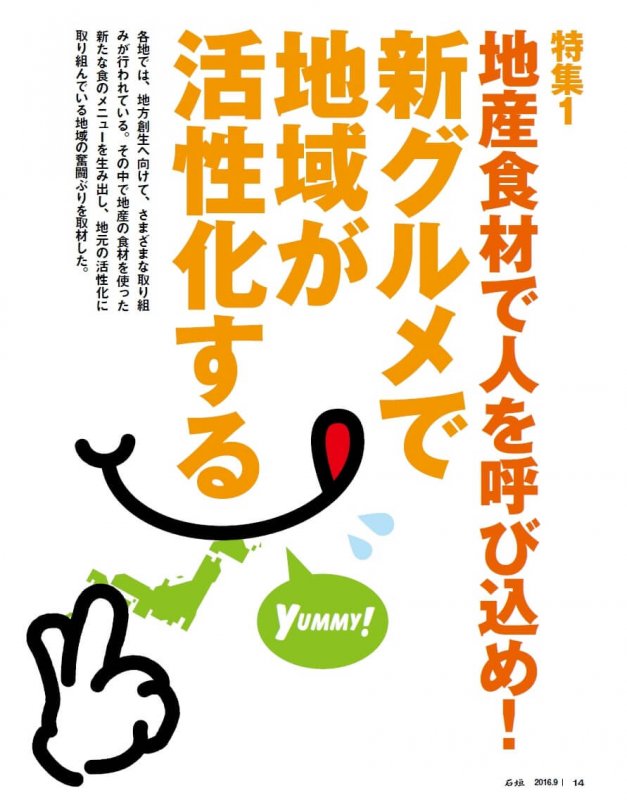各地では、地方創生へ向けて、さまざまな取り組みが行われている。その中で地産の食材を使った新たな食のメニューを生み出し、地元の活性化に取り組んでいる地域の奮闘ぶりを取材した。
総論 新・ご当地グルメ成功の可否を握る絶対条件がある!
ヒロ 中田(ヒロ・ナカタ)/リクルートライフスタイル 営業統括本部 旅行営業統括部 地域創造部 じゃらんリサーチセンター エグゼクティブプロデューサー
その土地でしか味わえない料理を求めて観光客が殺到する――全国各地でそんな光景をつくり出しているのが、じゃらんリサーチセンターのヒロ中田さんだ。プロデューサー役の中田さんが「新・ご当地グルメ」と名付けた料理は、商工会議所をはじめ、自治体、農・漁業者、飲食店関係者らが一体となってつくり上げている。
担当者の熱意で成功した2つの創作カレーメニュー
その土地でしか食べられないことをうたうご当地グルメは数多くあるが、食材の調達先を、その土地に限っていない例は珍しくない。また、地産地消としていても、提供時期が限られることもある。地元で調達できる食材の種類や量が少ない、旬の期間が短いといった理由があるのだろうが、それは提供側の言い訳にすぎず、観光客は不満を抱く。そこで中田さんは、「新・ご当地グルメ」の導入を提唱している。
「新・ご当地グルメ」とは、郷土料理とは異なる目的を持って新しく開発する企画開発型メニューのこと。目的は地域経済の活性化にあり、いつ行っても味わえる、地場食材に徹底的にこだわる、昼食として提供する、おもてなし料理である、明確なコンセプトと定義・ルールを持ち組織で運営する、といった厳格な基準を満たす必要がある。
「新・ご当地グルメ」第一弾は、まちおこしの一環として平成17年7月から提供を始めた北海道美瑛(びえい)町のつけ麺タイプの「美瑛カレーうどん」だった。美瑛産の小麦、豚肉、野菜というように香辛料以外の食材をすべて町内で調達した。 「そのころ北海道には212の市町村があったのですが、ご当地グルメはほとんどなかった。寿司、ラーメン、カニ料理、ジンギスカン、三平汁などが有名だったものの、すべて〝道内の共通メニュー〟だった。そのため、地域性を生かしたご当地グルメがあってもいいのではないかというところから議論が始まりました」と中田さんは当時を振り返る。
北海道は日本一の小麦の産地だが、うどんの文化がなかったことから、パン用の香麦(こうむぎ)という品種の美瑛産小麦を100%使ったうどんにビジネスチャンスがあるのではないかと考えた。地元の人から見れば突飛(とっぴ)な提案だったが、中田さんの提案に共感した建設会社の社長が町内の意見をまとめ、製粉所と製麺所の協力も取り付けた。
その翌年、成功を目の当たりにした富良野市が協力を求めてきた。富良野ではすでに有志が「食のトライアングル(農・商・消)研究会」を立ち上げて、主要産品のタマネギやニンジンを使ったカレーを提供していた。地元高校生による「ふらのカレンジャー娘」というユニットを結成して広報活動に努めたこともあり一時は話題になったものの、3年ほどで下火になっていた。中田さんはカレーメニューの内容が曖昧で、地場産食材のこだわりも店によりまちまちだったことが敗因と分析していた。
「それでもカレーでまちおこしをしたいという依頼でしたので、改めて地場産の米と野菜を使うことを徹底し、新たに卵を加えたオムカレーにすることを提案しました」
中田さんが当初示した定義・ルールは厳格な10カ条で、地元メンバーをひるませた。それでも受け入れる方向で議論を重ね、どうしても無理な条項を外して、米は富良野産を使い〝ライス〟に工夫を凝らす、卵は原則富良野産を使いオムカレーの中央には旗を刺す、富良野産のチーズ・バター、もしくはワインを使う、野菜や肉も富良野産か北海道産にこだわる、カレー料理にはふらの牛乳をつける、料金は税抜き1000円以内に設定するという6カ条を定めた。
「富良野オムカレー」の開発が終わると、首長と提供店舗8店(現在は9店)の協定書調印式をメディア向けに設定して知名度を高め、平成18年3月から各店が提供を開始。売れ残りを心配する店舗が数量を絞ったためゴールデンウイークに食べられなかったお客さまからクレームが来たり、牛乳を勝手にウーロン茶に変える店が出たりと、滑り出しは順風満帆ではなかったが、こうした問題点を定例会議などで共有し改善を図っていった。
「まちおこしは、やはり官民の合意形成があった方がやりやすい。それには熱意のある行政側のリーダーがいないと難しい。富良野は担当者に熱意があったので、現在まで人気メニューとして続けることができました」
成功した地域に共通する3つの力
中田さんは「手掛ける商品(メニュー)には自信がある」と胸を張る。「これまで70以上の商品をつくりましたが、後悔するものはありません。でも商品力があっても成功しない例はある。それは提供店舗力や事務局力が不足していたためです。特に提供店舗力は見極めが難しく、モチベーションアップも簡単ではありません。そもそも飲食店はライバル関係にあるので、協力して何かを成し遂げることに慣れていません。事務局は多くの場合、役所や商工会議所が担当するのですが、担当者の意欲や取り組む姿勢が重要です。市役所と町役場との比較では町役場の方が組織が小さい分だけ話がまとまりやりやすい。町の方が生き残りに必死という事情もありますね」
では商品力のあるメニューはどのようにつくられるのだろう。「私はプロデューサーとして商品のイメージを持って会議に臨んでいますが、それを最初に伝えることはありません。会議に出席した料理人に宿題を出して、次の会議までに考えてもらう。それを繰り返します。アイデアが出なければ私から提案することもありますが、そこで止まってはダメで、私のイメージと料理人のアイデアが化学反応を起こして、より良い料理が生まれることが理想です」
これまで仕掛けた数多くのご当地グルメから中田さんが選ぶベスト3は「美瑛カレーうどん」「富良野オムカレー」、青森県深浦町の「深浦マグロステーキ丼」だという。野球選手でいう走攻守、つまり商品力、提供店舗力、事務局力を兼ね備えている。その中のベスト1は24年の提供から4年目で13万食を突破した「深浦マグロステーキ丼」だ。
「新・ご当地グルメがうまくいかないと、商品が悪いという批判が必ず出ます。他責にしたがる気持ちは分かりますが、現実には提供店舗力か事務局力のどちらか、あるいは両方が悪いのです」
それに対し深浦は「取り組む姿勢が素晴らしい」と評価する。「今でも店と事務局が毎週会議を開いて情報を交換しているし、私の元には毎日の食数報告が届きます」
情報交換と数量報告を続けているということは、店と事務局が当初の熱意を維持して改善を続けているということ。「そのため最近手掛けた地域には2週間に1度の定例会議開催と毎日の数量報告を義務付けています。それをやらないところは下り坂になりますよ」
しかしベスト1の深浦にも課題はある。「それはブランド化です。隣の大間のマグロはブランド化されていて価格も日本一高い。大間という地名も多くの人が知っています。ところが深浦は全国的には知名度がゼロに等しい。ブランド化の目的は深浦のマグロの存在を全国に知らしめて価値を高めることです。富良野は10年、美瑛は11年続いていますが、今は20年まで頑張れと言っています。20年継続したら次は30年。それでようやく本物になれます。深浦も30年頑張れば、全国に知られるようになるでしょう」
食材だけでは優位性を保てない時代
中田さんが現在手掛けている「新・ご当地メニュー」は3つ、北海道古平町、島根県安来市、青森県東通村で開発が行われている。古平町では積丹半島で獲(と)れるホッケを使った「古平ホッケ刺身(さしみ)膳」を来年6月から提供すると決まった。ホッケの刺身を食べたことがある人は少ないだろう。鮮度を保つことが難しいことと寄生虫がいるという問題があり、限られた高級料理店が提供する程度である。消費者が手にするのはほとんどが「開き」だからこそ、ホッケの刺身には「引き」がある。新鮮な刺身を提供するためには、非常に手間が掛かる。
「しかしその分、参入障壁が高くなり、他の地域が簡単にはマネができなくなります。米についても生産者の協力により古平米が使えるシステムができました。もし魚や米の流通システムが構築できなければ、このメニューは誕生しません」
美瑛カレーうどんや富良野オムカレーのマネは、それほど難しくない。ただ競争が緩やかな時代に始めて知名度を高め定着させたから、現在でも優位性を保っていられるのだ。競争が激しい最近は、参入の障壁を高めるために商品の設計自体を変えているという。
「商品を開発するときは食材を見て、まずネーミングから考えます。ネーミングがそのままメニューの名前に採用されるとは限りませんが、最初に商品がイメージできるかどうかが重要なのです。食材を見てイメージできなければやめた方がいいと、アドバイスすることもありますよ」
食をテーマにしたまちおこしは、簡単ではない。食材の良さだけでは勝てず、提供店舗と事務局の「覚悟」が問われる。その覚悟さえできれば、成功が見えてくる、というのが中田さんの持論のようだ。