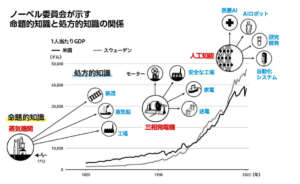1月13日に投開票された台湾総統選は、民主進歩党の頼清徳(らいせいとく)氏が当選したが、頼氏や民進党の圧勝ではなかった。日本で盛んに報道された中国からの軍事的圧力に台湾市民が憤り、危機感を高めていれば、頼氏の地滑り的大勝利となっていたはずだが、頼氏の得票率は40%強。2020年の前回総統選挙で蔡英文(さいえいぶん)氏に敗れた国民党の韓国瑜(かんこくゆ)氏の得票率(39%)と変わらない歴代最低得票率の総統となった。
第2位の国民党の侯友宜(こうゆうぎ)候補との票差は約91万票に過ぎず、侯氏と民衆党の柯文哲(かぶんてつ)氏との候補者一本化が成功していれば、頼氏の当選は危うかっただろう。同時に行われた立法委員選挙では国民党が第1党となり、議席を減らした民進党は少数与党に転落した。 一連の結果が示すのは「台湾のニューノーマル」かもしれない。筆者は昨年4回、仕事や休暇で台湾に足を運び、総統選直前の年初も台北に滞在していた。印象論に過ぎないが、50歳代以上の世代が台湾の在り方や中国に対して明確な政治姿勢を持ち、政治に熱くなれるのに対し、10~30歳代は民進党、国民党のいずれにも強い支持は示さず、第3党の民衆党にも冷めていたという点だ。
若者の総統選への熱量も従来に比べて大きく下がったように感じた。少なくとも14年に中台間の「サービス貿易協定」批准を巡って学生が立法院を占拠した「ひまわり学生運動」の時の熱量ではなかった。投票率も71・86%と前回を3ポイントも下回り、世界の高い関心とは逆に台湾市民はそれほど盛り上がってはいなかった。
要は、習近平政権の台湾への強硬姿勢、軍事圧力に正面から対峙(たいじ)し、軍事的に押し返すことは、米国や同盟国の強力な支援があったとしても現実的ではない一方、中国共産党の厳しい統治で窒息する香港のような未来は拒否する。蔡英文政権の8年間のように「中国と対峙はしても挑発はせず、TSMCを中心とする半導体産業をグローバル展開し、台湾の存在感を高める」というソフトな安全保障戦略であり、「現状維持(Status Quo)」志向ともいえるだろう。若者には燃えにくい政治的な方向だ。
今回、同一政党が初めて連続3期で政権を担うことになった点はもともと長期政権を嫌う台湾市民が「現状維持」のため、妥協の上で受け入れた結果であり、汚職など長期政権の問題は立法委員選挙で牽制(けんせい)したということなのかもしれない。「台湾のニューノーマル」をしっかり観察していきたい。