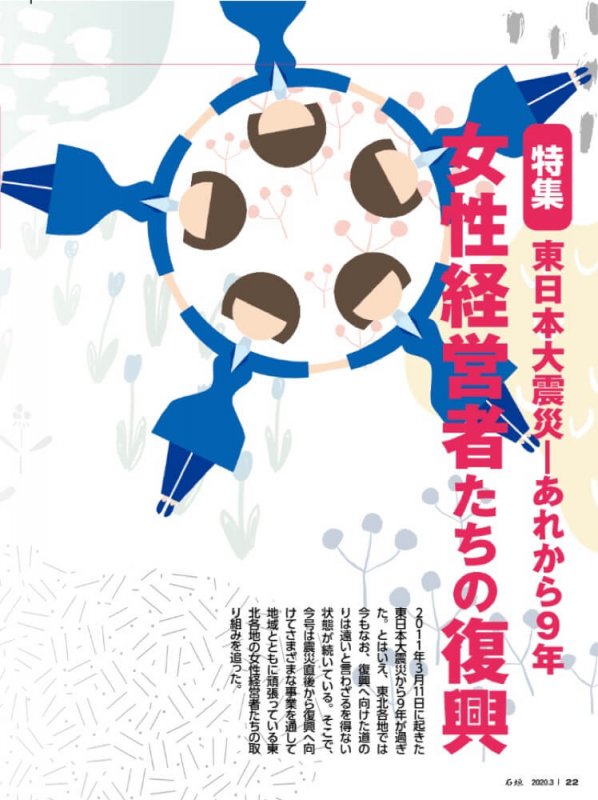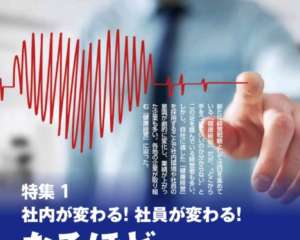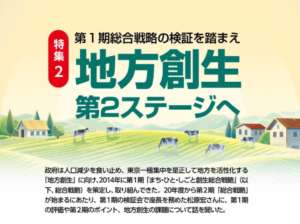2011年3月11日に起きた東日本大震災から9年が過ぎた。とはいえ、東北各地では今もなお、復興へ向けた道のりは遠いと言わざるを得ない状態が続いている。そこで、今号は震災直後から復興へ向けてさまざまな事業を通して地域とともに頑張っている東北各地の女性経営者たちの取り組みを追った。
総論 地域で活躍する女性のネットワークを生かして支援活動に尽力
井上 弓子(いのうえ・ゆみこ)/みやぎ・やまがた女性交流機構 会長
宮城・山形両県のさまざまな分野で活躍する女性が中心となって、2009年に設立された「みやぎ・やまがた女性交流機構」。両県の活性化を目指して連携をとってきたが、東日本大震災以降、交流を通じて築かれた幅広い人脈やネットワークを生かして、被災者の視点に立った復興支援活動を展開している。
働く女性たちの意識を高めて地域経済を元気に
みやぎ・やまがた女性交流機構は、宮城県、山形県、仙台市、山形市、宮城県商工会議所連合会、山形県商工会議所連合会、東北経済連合会で構成する「宮城・山形地域連携推進会議(現:宮城・山形未来創造会議)」が開催した“交流会”として活動をスタートし、その後、民間団体として独立した。人口減少が加速する中、意欲ある女性の活躍をサポートし、業種を超えたネットワークを築いて両県の活性化を図ろうと、毎年2月に交流会を開催してさまざまな課題に取り組んできた。同機構の設立時から会長を務めてきたのが、山形市に本社を置く髙島電機会長で、山形商工会議所女性会の会長も務める井上弓子さんだ。井上さんは当初の目的をこう説明する。
「意外かもしれませんが、山形県の女性(25〜44歳)の就業率は全国2位(2015年国勢調査より)と高いんです。それはお父さんの収入だけでは暮らしていけないから。それで家計を助けるために、フルタイムで働く女性が非常に多い。にもかかわらず、自分の仕事を“補助的”と捉えていて、社会で活躍しようという意識は高くありませんでした。それを女性が主体となって引き上げ、地域経済を元気にしようというのが機構の狙いでした」
交流会で話し合ってきた課題の一つに、女性が働くための会社の環境整備があった。そこで、地域で活躍する女性起業家やNPO法人代表、ボランティア活動に携わる人などを招いて話を聞き、交流する中から、具体的なヒントやアイデアを模索するなどしていた。
そうして11年、5回目の交流会が無事終わった翌月、東日本大震災が起こった。
日ごろ培ったネットワークを駆使して支援活動を展開
震災直後は、首都圏から東北に向かう鉄道や高速道路がストップし、なかなか復旧のめどが立たなかった。3月といえば年度末である。髙島電機では、電気工事会社に納品する材料の輸送が滞り、てんてこ舞いだった。その一方で井上さんのところには、交流のある女性たちから盛んに電話が掛かってきた。山形は幸い大きな被害を受けず、東京から宮城方面へ向かう人や物資の拠点となっていたため、「私にも何かできることはないか?」と問い合わせてきたのだ。井上さんは日ごろ培ったネットワークを生かし、すぐに支援活動に乗り出した。
例えば、山形の機構の仲間たちは被災地の人に温かいものを食べてもらおうと、手づくり料理を取りまとめて、宮城の同機構メンバーに届けに行った。また、別のメンバーは気仙沼や南三陸、石巻など宮城県北部沿岸地域に赴き、仮設住宅に住む被災者向けにコミュニティ支援活動を展開した。
「ほかにも、ボランティア活動をしているNPO法人の女性たちは、支援物資を何度も運ぶうちに、被災地に必要なのは仕事だと気付き、がれきの撤去や解体、清掃活動や朝市の運営、高齢者の見守り業務を始めて、100人以上の雇用を創出しました。また、育児サークルを運営している女性は、山形に避難してきた親子と積極的に交流するなど、自分の経験や強みを生かした活動にいち早く乗り出していました」
女性たちによるさまざまな支援活動は、「東日本大震災からの復興、私たちができること」をテーマに掲げた、2011年の仙台市での第6回交流会の場で紹介された。また、同機構メンバーがコーディネーターとなり、被災地で見たり聞いたり体験したことをヒアリングして、復興に向けた課題やそれぞれの思いなどを活発に意見交換した。
「人と人との絆、日常への感謝、生活、情報、備えなど、被災地の女性たちから寄せられた声から強く感じたのは、東北人の誇りです。東北人は、長い冬を乗り越える知恵を持っています。だからこそ、あんな大災害に遭っても冷静に行動したり、協力し合ったりできたのだと思いました」
交流会をきっかけに新たなメニューや商品が誕生
これらの貴重な声や体験談を、広く一般の人にも知ってもらおうと企画したのが、12年1月に仙台市で開催したパネル展だ。第6回交流会の様子や、復興支援に取り組む女性たちの活動をまとめたパネルを数多く展示した。ほかにも、復興支援の一環で生まれたタオル人形「元気でいてケロちゃん」や「エコたわし」などの手づくり体験コーナーを設けて、多くの人が気軽に立ち寄れるように工夫した。会期中は多くの人が訪れ、好評を博したことから、その後も山形大学、山形商工会議所、埼玉県や千葉県の自治体などにもパネルを貸し出し、巡回展が行われた。
震災以降、女性たちによる復興支援活動を通じて、宮城と山形両県の連携はより密なものになったという。交流会の席であがったアイデアが具体的な形になることも増えてきた。
その一つが、地域の伝統野菜の積極活用だ。農家レストランを営む女性が、「今の若い女性は冷蔵庫に食材がないと何もつくれない」と問題提起したことをきっかけに、東北各地にある乾物などの保存食材に着目。昼食交流に各地の食材を運び込み、シェフは若い世代のためにおしゃれなレシピを開発してくれた。
また、「福島の復興なくして東北の復興なし」との思いから、4年前に交流会に参加した福島県の女性たちが集めて提供してくれたあんぽ柿から、「あんぽ柿タルト」の商品化も実現した。
「あんぽ柿は福島県の特産品の一つですが、柿を干している間に放射能を吸収してしまい、震災後しばらくは出荷できなかったそうです。今は数値も落ちて出荷できるようになったので、多くの人にまた食べてもらいたいと考案したのが、あんぽ柿でつくったタルトです。交流会の料理を担当するシェフがレシピをつくり、皆で試食をしたら、おいしいと大好評。福島県北の新たな銘菓として売り出すことが決まりました」
細く長く続けることが大切
震災復興のさまざまな活動や支援に関わってきた井上さんだが、9年がたった今、震災の記憶が薄れていくのを感じているという。被災地に住む人でさえ、日常の中で忘れてしまっている、という声をよく耳にするそうだ。
「人間ってすぐに忘れてしまう生き物です。それでも、震災の経験や教訓を今後に生かしていくには、忘れずに細く長く続けていくことが大切です。そういうのは女性の方が得意だと思います」
現在、女性の活躍の場は広がっており、そのステージも会社だけでなく、NPO法人やサークル、ボランティア団体と多様になっている。そこで培われた経験やスキルは災害時などに力を発揮する。そういう意味で、同機構を通じてつながった女性たちのネットワークは、いざというときにセーフティーネットの役割を果たす可能性を秘めている。
同機構が発足して11年が過ぎ、「そろそろ若い人たちが引き継いでいく時期」と井上さんは考えている。昨年は新たな試みとして、交流会に女子高生や女子大生が参加したほか、オブザーバーとして初めて男子学生も加わって意見を交換した。現在の東北の大きな課題である若者の流出を食い止めるために、雇用の創出や地域の魅力の再発見など、思った以上に若い世代がしっかりとした意見を持っていて、頼もしく感じたという。
「震災を経て改めて認識した人と人との絆を大切にしながら、各方面で活躍する人たちとのつながりをもっと広げ、持続可能な社会を実現できるように、今後もバックアップしていきたい」と、井上さんは穏やかな笑みの奥に、強い意志をのぞかせた。