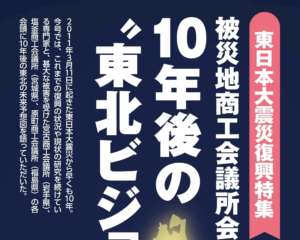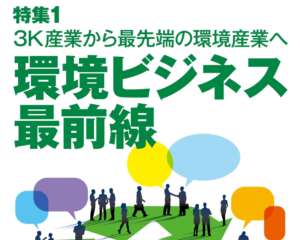事例2 パートナー企業と共に社会的課題の解決を目指す
オムロン
パートナーシップ構築宣言の冒頭には、「直接の取引先を通じてその先の取引先に働きかける(「Tier N」から「Tier N+1」へという取り組み)ことにより、サプライチェーン全体での付加価値向上に取り組む」という一文がある。オムロン取締役会長の立石文雄さんが語る同社の姿勢は、まさに宣言の実現を目指すものだった。
製造業が直面するサプライチェーンの四つの課題
―製造業が直面する課題をどう認識されていますか。
立石文雄会長(以下、立石) 日本の製造業の状況、特にサプライチェーンの観点から課題を四つ挙げたいと思います。
一つ目は、階層型からネットワーク型へのバリューチェーンの変革です。この課題については、従来の大企業を頂点とする「階層構造」から、企業間での情報共有や協業が進む「水平構造」への変化の動きが見られます。デジタル技術をうまく活用しながら、中小企業が特定の大企業のみならず、さまざまな主体と連携していくことで、新たな価値を創造する「ネットワーク型のバリューチェーン」を構築していきます。
二つ目は、日本の産業の国際競争力の維持・強化です。サプライチェーンのグローバル化が拡大し、そして複雑化しています。ポストコロナの世界においても、リスク回避のための分散化や多元化が加速すると考えています。こうした点を踏まえながら、日本の製造業の「国際競争力」を維持・強化していく必要があります。
三つ目は、中小企業での高齢化・人手不足問題です。日本の経済・産業・雇用を支える中小企業において、今、高齢化や人手不足の問題が、深刻化しています。「生産性の向上」「事業承継」「技能継承」への対応が急務です。
四つ目は、業務の自動化・非接触化といったデジタル強靭(きょうじん)化です。コロナ禍では、感染拡大抑制のため、「人と人との接触機会の抑制」が求められました。サプライチェーン全体で業務の自動化・非接触化といった、「デジタル強靭化」を徹底的に進めていくことが欠かせません。
大企業・中小企業が互いの強みを生かして課題を解決
―そうした課題に対し、「大企業の果たすべき役割」とは、どのようなものですか。
立石 大企業の果たすべき役割として、特定の大企業を頂点とするサプライチェーンの階層構造を、フラットなネットワーク型に変えていく「仕組みの変革」と、中小企業のデジタル化推進のために、IT系の知識や経験に富む人材の派遣を含めた支援を強化すること。つまり、「支援」の両面があると考えます。国が豊かになるためにも、「中小企業の生産性向上」を大企業が支援していくことが大切です。
―2020年8月、オムロンは「パートナーシップ構築宣言」を策定・公表しました。宣言に込めた思いや狙いを教えてください。
立石 社会的課題が山積し、一方で変革のスピードが速まっている中で、より良い社会を目指すためには、自社だけでは限界があります。そこで、中小企業をはじめとする「パートナー企業」と共にオープンイノベーションを起こし、社会的課題の解決を目指すことを宣言に盛り込みました。
―立石さんがお考えになる「パートナー企業」とのあるべき姿とは、どのようなものですか。
立石 フラットに一緒になって共に社会的課題に立ち向かい、互いの強みを生かして、スピーディーに解決する関係性です。パートナーシップによって社会的価値を高め、その結果として、パートナー企業とオムロンが共に企業価値を高めていきます。そして、さらに新たな社会的課題に挑戦し続ける、そんな「円環的」かつ「持続的」な成長を続けられる姿を描いています。
コロナ禍で苦しむ顧客を支援する取り組み
―パートナー企業が直面する課題は、どのようなものですか。
立石 冒頭で製造業の課題をお話ししましたが、それは製造業の大半を占める中小企業が解決すべき課題でもあります。経団連のサプライチェーン委員会で議論している課題は、中小企業の商流・金流における「デジタル化の遅れ」、後継者をはじめとする人材不足(特に技能・技術の面で顕著)、そして、生産性についてです。当社では、パートナー企業が抱える課題について、事業活動を通じて、顧客やサプライヤーから把握するように努めています。
特に国が推進するDX(デジタルトランスフォーメーション)の対応では、(当社でも人材が十分に育っているというわけではありませんが)人材供給や技術のサポートができるのではないかと考えています。例えば、大企業が連携して講師となって、中小企業に技術やノウハウを教え、人材を育てる「教室」を開くという方法もあると思います。
―終わりが見通せないコロナ禍にあり、オムロンの社会的課題解決に対する取り組み支援や連携について教えてください。
立石 食品企業におけるロボット導入事例、除菌作業代行、遠隔診療の三つを紹介します。
ロボット導入事例には、冷凍ケーキを開発・製造・販売する食品会社の例があります。まず当社のSEが現場に入り、調査・分析に基づく提案を行いました。続いて東京のプルーフ・オブ・コンセプト・ラボ(実機モデルを使って顧客と課題解決策を実証する施設)で検証を行いました。その結果、職人技のケーキの盛り付けをロボットが代行することに成功し、「人手不足の解消」に貢献できました。その結果、菓子職人が、ヒトにしかできない新しい商品開発に一層注力できるようになったと聞いています。
除菌作業代行は、除菌作業の従事者をはじめとする人々の感染症リスクの低減に貢献した事例です。紫外線照射ロボットを製作するパートナー企業には、モバイルロボットを提供しています。現在、世界20カ国以上で展開中です。
遠隔診療は、オムロンの「電子血圧計」などで収集したデータを医療従事者と共有することで、通院時の感染リスクを避ける、遠隔診療を実現しました。
―今後のパートナー企業との関係や展望などについて、お聞かせください。
立石 製造業の立場から申し上げると、従来の大量消費を前提とした大量生産で、世界中の人々を豊かにしてきましたが、一方で大量廃棄による環境問題など、未来の社会に暗い影を落としています。工業社会がもたらした「負の遺産」を払拭(ふっしょく)するため、これまでの生産から廃棄までの直線的な「リニア・エコノミー」から、循環型の「サーキュラー・エコノミー」へと変えていく必要があると考えます。
中長期的にはこの大きな社会的課題にも、パートナー企業と共に、取り組んでいきたいと考えています。
会社データ
社名:オムロン株式会社
所在地:京都市下京区塩小路通堀川東入
※月刊石垣2021年3月号に掲載された記事です。